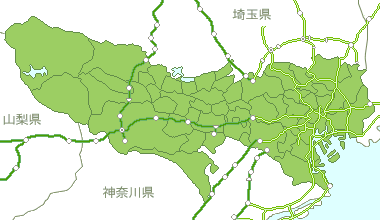神社・寺院・歴史 一覧

-
い 易行院
- [ 寺院 ]
-
足立区東伊興4-5-5
足立区東伊興にある浄土宗寺院
日照山易行院不退寺と号し、芝増上寺末。歌舞伎では有名な助六とその愛人揚巻。ふたりの仲の良さから「助六と揚巻
-
い 石川啄木歌碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
台東区西浅草1-6-1 等光寺内
浅草の夜の寂寥感をうたった歌碑。
歌碑は、啄木生誕七十年にあたる昭和三十年に建てられた。「一握の砂」から次の句が記される。等光寺の境内にあり
-
う 宇喜多秀家の墓
- [ 歴史 ]

-
八丈町大賀郷
関ヶ原の戦いにて破れた豊臣五大老の一人、宇喜多秀家の墓
豊臣家5大老のひとり、宇喜多秀家が埋葬されている。彼は1606(慶長11)年、33歳の若さで主従13人とと
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
杉並区大宮2-3-1
境内は15000坪と都内3番目の広さを持つ古社。
康平6年(1063年)に源頼義が前九年の役の帰途、石清水八幡宮から分霊して当地に創建。御祭神に親子三神をお
-
お 大森貝塚
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 | 庭園 ]
-
品川区大井6-21-6
1877年、日本で初めて発掘された貝塚跡。
アメリカ人の動物学者・エドワード・S・モースが、1877年(明治10年)6月19日に横浜から新橋へ向かう途
-
お 小野照崎神社
- [ 神社 ]
-
台東区下谷2-13-14
江戸時代の富士山信仰が残る神社。
小野篁を主祭神とし、相殿に菅原道真を祀る。852年(仁寿2年)この地の住民が上野照崎の地に小野篁を奉斎した
-
き 旧前田侯爵邸洋館
- [ 歴史的建造物 ]
-
目黒区駒場4-3-55 駒場公園内
旧加賀藩主で前田家第16代当主の前田利為の本邸として昭和4年(1929)に洋館が、昭和5年に和館が竣工。洋
-
し 芝東照宮
- [ 神社 ]
-
港区芝公園4-8-10
1641(寛永18)年創建。祭神は徳川家康。神体は徳川家康寿像。旧社格は郷社。日光東照宮、久能山東照宮、上
-
し 芝大神宮
- [ 神社 ]

-
港区芝大門1-12-7
東京十社の1社で、旧社格は府社。
伊勢神宮の内外両宮の祭神を祀ることから、関東における伊勢信仰の中心的な役割を担い、「関東のお伊勢様」として
-
ぞ ゾウの遺跡
- [ 歴史 ]

-
御蔵島村村里
北海岸、高さ50mの断崖上の縄文期の遺跡。
約64年前の遺跡とされ、ここから多数の縄文式土器や石器が見つかっている。三宅島や本土の方向を眺められるこの
-
な 南谷寺
- [ 寺院 ]
-
文京区本駒込1-20-20
元和2年(1616年)に比叡山の南谷にいた万行律師によって開かれた寺。寛永年間(1624~44)三代将軍家
-
な 成田山深川不動堂
- [ 寺院 | 不動 | パワースポット ]
-
江東区富岡1-17-13
真言宗智山派成田山新勝寺の東京別院。通称は深川不動尊、深川不動堂。
元禄16年(1703年)、1回目の成田不動の「出開帳」が富岡八幡宮の別当・永代寺で開かれた。これが深川不動
-
ほ 宝泉寺(日野市)
- [ 寺院 ]
-
日野市日野本町3-6-9
鳥羽伏見の戦いで戦死した井上源三郎の墓・顕彰碑がある寺。
墓前には子孫が管理している「墓前ノート」があり、全国から訪れたファンのメッセージがつづられています。臨済宗
-
う 牛嶋神社
- [ 神社 ]
-
墨田区向島1-4-5
本所地域の総鎮守の神社。
創建は貞観二年(860)と伝えられ関東大震災後の隅田堤の拡張により墨堤常夜灯の下の大銀杏のある場所(向島須
- [ 寺院 | 不動 ]
-
江戸川区平井1-25-32
通称「目黄不動尊」、正式名称は「牛宝山(ごほうざん)明王院最勝寺」貞観2年(860年)、円仁(慈覚大師)に
-
だ 第二次大戦戦跡
- [ 歴史 | パワースポット | 心霊・不思議・廃墟 ]

-
小笠原村父島
トーチカ・砲台等が残っている
第二次世界大戦中小笠原はアメリカ軍との戦争の舞台となり、父島・母島は激しい攻撃を受けました。島には当時の日
-
の 乃木神社(港区)
- [ 神社 ]

-
港区赤坂8-11-27
乃木希典将軍と乃木静子夫人を祀る神社。
空襲により本殿以下社殿が焼失したが、昭和37年に復興。日露戦争で活躍した乃木希典将軍とその妻静子夫人がまつ
-
び 毘沙門天善國寺
- [ 寺院 ]

-
新宿区神楽坂5-36
神楽坂で親しまれる毘沙門さま。文禄4年(1595年)、徳川家康によって創建された日蓮宗の寺院。山ノ手七福神
-
む 武蔵国分僧寺跡
- [ 寺院 ]
-
国分寺市西元町1
大正11年に国指定史跡に指定。
天平13(741)年、聖武天皇によって建立された古刹跡。通称:国分寺跡。かつては約50万平方メートルの広大
-
り 龍光院(江東区)
- [ 寺院 ]
-
江東区三好2-7-5
深川七福神のひとつ。
慶長16年(1611)馬喰町(中央区)に創建された浄土宗の寺院。明暦3年(1657)の大火で全焼したため神
-
り 龍源寺
- [ 寺院 ]
-
三鷹市大沢6-3-11
新選組局長近藤勇の生家宮川家の菩提寺。
曹洞宗の寺で勇の生家宮川家からほど近い。境内には勇の胸像と天然理心流の碑が建ち、墓参りをする人が絶えない。
-
お 大観音寺
- [ 寺院 | 観音 ]
-
中央区日本橋人形町1-18-9
願いの地蔵尊は祈願成就のご利益が、韋駄天尊はアスリートの聖地として、いつでも参拝できるよう一晩中灯かりが灯
-
き 喜之床跡
- [ 歴史 ]
-
文京区本郷2-38-9
石川啄木が明治42(1909)年より、妻・子・母を上野駅に迎え、2年2ヶ月過ごした住居の跡。旧家屋は春日通
-
ね 根津神社
- [ 神社 | ツツジ | パワースポット ]

-
文京区根津1-28-9
つつじの名所として有名。
日本武尊が1900年近く前に創祀したと伝える古社で、東京十社の一つに数えられている。徳川5代将軍綱吉により
- [ 歴史的建造物 | 美術館・ギャラリー ]

-
千代田区霞が関1-1-1 法務省赤れんが棟
法務史料、建築資料及び広報資料などを展示。
法務省旧本館は、1895(明治28)年にドイツの高名な建築家により竣工した官庁建築。戦災によりれんが壁と床
-
よ 要津寺
- [ 寺院 ]
-
墨田区千歳2-1-16
臨済宗京都妙心寺の末寺。
臨済宗、京都妙心寺末で、慶安年間(1648-1651)に僧東鉄が本郷に創建。天和2年(1682)に焼失して
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 ]
-
墨田区堤通2-6-10
墨堤通りに面した小さな公園。
幕末時代、新政府に対抗して独立政府を宣言して戦った榎本武揚の銅像が建つ。向島を愛した榎本は、晩年を向島で過
-
げ 源空寺
- [ 寺院 ]
-
台東区東上野6-19-2
徳川家康公開基。
浄土宗の源空寺は、五台山文殊院と号し、天正18年(1590)湯島に草創した浄土宗の寺。境内には、伊能忠敬、
-
ち 長久寺
- [ 寺院 ]

-
利島村
僧日想が1505(永正2)年に建立した日蓮宗下田本願寺の末寺。
島民の菩提寺でもあり、明治10年代には教育の学び舎として利用された。境内には松の大木あり。
-
ま 松之大廊下跡
- [ 歴史 ]
-
千代田区千代田1-1
松之大廊下があった場所には所在を示す碑が建てられている。
忠臣蔵でおなじみの元禄14年(1701年)3月14日赤穂藩主・浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)