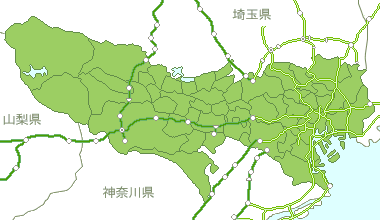神社・寺院・歴史 一覧

-
す 季重神社
- [ 神社 ]
-
日野市平山6丁目
平山季重を祀った季重神社。
平家物語で有名な“一ノ谷の合戦”で活躍した武将・平山季重を祭った神社。古くは日奉(ひまつり)明神社と呼ばれ
-
と 東郷神社
- [ 神社 ]
-
渋谷区神宮前1-5-3
昭和33年(1958年)に奉賛会が結成され、昭和39年(1964年)に社殿が完成した。日露戦争の日本海海戦
-
に 日本民藝館
- [ 歴史 ]

-
目黒区駒場4-3-33
国内外の陶磁器、織物、染物、木漆工、絵画、竹工、金工、ガラスなど、約1万7000点を収蔵
宗教哲学者柳宗悦[やなぎそうえつ]らが創設。陶磁、染織、木漆、絵画など約1万7千点を所蔵し、沖縄の染織、古
-
あ 赤坂氷川神社
- [ 神社 ]

-
港区赤坂6-10-12
旧社格は府社で東京十社の一つ。
天暦5(951)年創立。現在の社殿は徳川家8代将軍吉宗の命により、現在地に遷された。都重宝社殿。同区内白金
-
お 青梅山金剛寺
- [ 寺院 ]

-
青梅市天ヶ瀬町1032
平安時代に平将門の開基とされる古刹。
東京都の有形文化財(昭和36年1961年指定)の四脚門をくぐると正面に本堂、右手には庫裏があります。境内で
- [ 神社 ]
-
墨田区文花2-5-8
地元の梅の名所として知られている。
経津主大神を御祭神として、民業指導、海上守護などの神様として広く仰がれている。旧・小村井村の鎮守で、平安時
- [ 神社 ]
-
江東区亀戸3-57-22
1000年の時を経て今も「勝矢祭」が守り伝えられている神社。
天慶の昔、平将門が乱を起した時、追討使俵藤太秀郷はこの香取神社に参拝し戦勝を祈願した。乱はめでたく平定する
-
き 旧朝倉家住宅
- [ 歴史的建造物 | 庭園 | 花 ]
-
渋谷区猿楽町29-20
東京府議会議長や渋谷区議会議長を務めた朝倉虎治郎により大正8(1919)年に建てられた国の重要文化財。広大
-
げ 月窓寺
- [ 寺院 ]

-
武蔵野市吉祥寺本町1-11-26
吉祥寺の四軒寺の一つ。
曹洞宗系単立寺院の月窓寺は、雲洞山天暁院と号します。月窓寺は、牛込宝泉寺五世洞巌(寛文3年1663年寂)が
-
せ 世田谷代官屋敷
- [ 歴史 | 庭園 ]

-
世田谷区世田谷1-29-18
近江彦根藩世田谷領の代官であった大場氏の屋敷。
江戸時代中期、彦根藩世田谷領20ヵ村の代官を世襲した大場家の住居で、1978(昭和53)年に重要文化財に指
- [ 教会 ]

-
千代田区神田駿河台4-1-3
明治24(1891)年に建設された日本最大のビザンチン様式の聖堂。文久元(1861)年の来日後、半世紀以上
-
ほ 本妙寺(豊島区)
- [ 寺院 ]
-
豊島区巣鴨5-35-6
1572年(元亀2年)日慶が開山、徳川家康の家臣らのうち三河国額田郡長福寺(現在愛知県岡崎市)の檀家であっ
-
み 宮沢賢治旧居跡
- [ 歴史 ]
-
文京区本郷4-35-4
賢治が25歳時(大正10(1921)年)に上京後、約8か月住んだ二軒長屋跡。童話集「注文の多い料理店」に収
-
い 井草八幡宮
- [ 神社 ]

-
杉並区善福寺1-33-1
源頼朝ゆかりの神社。
青梅街道沿いにある神社である。祭神は八幡大神(応神天皇)。1664(寛文4)年に改築した本殿は、現在杉並区
-
え 圓福寺
- [ 寺院 ]

-
清瀬市野塩3丁目−51
大医山圓福寺。以前は別の宗旨の寺があったと伝えられていますが陽岳宗春が新しく開山し曹洞宗となりました。弘化
-
え 炎天寺
- [ 寺院 ]
-
足立区六月3-13-20
平安期の末に創建されたと伝わる寺。
江戸後期の俳人小林一茶が詠んだ「蝉鳴くや六月村の炎天寺」の舞台。「やせ蛙負けるな一茶是にあり」の句にちなみ
- [ 神社 ]

-
府中市宮町3-1
大國魂神社境内末社。元和4年(1618)、二代将軍秀忠の命によって造営された。徳川家康公歿後、駿河国久能山
-
か 寒山寺
- [ 寺院 ]

-
青梅市沢井2-748
寒山寺は中国の蘇州にある寒山寺にちなんでいます。
楓橋を挟んで小澤酒造の対岸に位置している。昭和5(1930)年に建立された、中国蘇州の寒山寺にちなんだ趣の
-
き 旧乃木邸
- [ 歴史的建造物 ]
-
港区赤坂8-11-32
乃木神社の隣にある乃木大将の邸宅。
木造3階建ての和洋折裏建築で、明治35(1902)年に新築され、乃木希典大将夫妻が大正元年(1912)9月
-
き 旧寛永寺五重塔
- [ 寺院 ]

-
台東区上野公園9-83
寛永8年(1631年)建立の初代の塔が寛永16年(1639年)に焼失した後、同年ただちに下総・古河城主土井
- [ 歴史 ]

-
三宅村北部
小金井市と三宅村を結びつける。
安政3年(1856)に博打の罪で流されてきた小金井小次郎が島民のために作った井戸。小金井小次郎は、「江戸末
-
じ 十三神社
- [ 神社 ]

-
新島村本村2-6-13
伊豆諸島の開祖、事代主命を主神として他に同系十ニ神が祀られています。
13の神が祀られる伊豆諸島随一の規模を誇る神社である。12月8日には例大祭が行われ、神楽と獅子木遣は都の無
-
と 富賀神社
- [ 神社 ]

-
三宅村神着199番地
三宅島の総鎮守、富賀山(海抜60.4m)の中腹に鎮座
三宅島を代表する神社の一つ噴火によって壊れた社もほぼ修復が終わりまた静かな佇まいを取り戻している。
-
は 花園神社
- [ 神社 | パワースポット ]

-
新宿区新宿5-17-3
新宿の街の中心にあり、新宿総鎮守として江戸時代に内藤新宿が開かれて以来の、街の守り神として祀られている。境
-
み 三囲神社
- [ 神社 ]
-
墨田区向島2-5
境内には雨乞いの句碑が立っている。
元禄6年(1693年)俳人の宝井其角が参拝に訪れた時、日照り困っていた地元の者の哀願によって、この神に雨乞
- [ 教会 | デート | イルミネーション | 祭り・イベント ]

-
港区南青山3-14-23
南青山の閑静な住宅街にたたずむ教会で、クリスマスが楽しめる。
クリスマス期間中、ゴールドのLEDを中心に、グリーン・レッドを織り交ぜた約10,000球のイルミネーション
-
も 森鴎外の墓
- [ 歴史 | その他 ]
-
三鷹市下連雀4-18-20
本名は林太郎。
東大医学部を卒業後、軍医としてヨーロッパに留学し、陸軍医務局長や陸軍軍医総監の地位に進む。その一方、文学に
- [ 歴史 ]

-
八丈町樫立
縄文時代の土器、石器のほか住居跡や埋葬人骨が出土した遺跡。
内地の同時代の出土品とは様相・特徴がまったく違い、同時代の文化圏の違いなどを考察する上でも重要なものとされ
-
お 大山福地蔵尊
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
板橋区大山町54
地蔵尊通りと川越街道の交差点近くにある大山福地蔵尊。
江戸時代にこの地で亡くなった旅人や馬の供養を行なった「お福さん」にちなんで建てられたもの。現在も大山の守り
- [ 神社 | 祭り・イベント ]

-
府中市宮町3-1
大國魂神社の例大祭は、関東三大奇祭の一つであるくらやみ祭りで大國魂神社最大のお祭り。東京都指定無形民俗文化