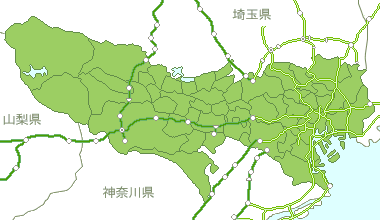神社・寺院・歴史 一覧

-
し 七人塚
- [ 歴史 ]
-
御蔵島村
謀反を計画した7人が埋葬されている。
宝暦年間(1751~1764)に御蔵島流刑になり島をのっとる企てをした8人の流人。謀反を計画した7人が埋葬
-
じ 浄土宗心行寺
- [ 寺院 ]

-
江東区深川2-16-7
深川七福神の福禄寿として知られる。
元和2(1616)年に観智国師の高弟、光蓮社団誉一路屋道上人の開山により京橋八丁堀に創立。寛永10(163
-
じ 十三神社
- [ 神社 ]

-
新島村本村2-6-13
伊豆諸島の開祖、事代主命を主神として他に同系十ニ神が祀られています。
13の神が祀られる伊豆諸島随一の規模を誇る神社である。12月8日には例大祭が行われ、神楽と獅子木遣は都の無
-
す 鈴ヶ森刑場跡
- [ 歴史 ]
-
品川区南大井2-5-6 大経寺内
鈴ヶ森刑場の跡地。
江戸の北の入口(日光街道)に設置されていた小塚原刑場、西の入口(甲州街道)沿いに設置されていた八王子市の大
-
ぞ 増上寺

- [ 寺院 | 初詣スポット ]

-
港区芝公園4-7-35
1393年の創建の江戸の大寺。
浄土宗の七大本山の一つで、徳川将軍家の菩提寺として知られる。戦災で多くの建造物が焼失したが、境内入口の三解
-
と 鳥越神社
- [ 神社 | 初詣スポット | 祭り・イベント ]

-
台東区鳥越2-4-1
例大祭に出る千貫神輿は都内最大級を誇る。
白雉2年(651年)、日本武尊を祀って白鳥神社と称したのに始まるとされる。毎年数十万人が集まる6月9日に近
- [ 寺院 | 碑・像・塚・石仏群 ]
-
豊島区巣鴨3-35-2
本尊は地蔵菩薩(延命地蔵)。とげぬき地蔵の通称で知られる。
慶長元年(1596年)、扶岳太助が江戸神田湯島に創建。1891年(明治24年)、巣鴨に移転。1945年(昭
-
と 豊川稲荷東京別院
- [ 稲荷 | 寺院 ]
-
港区元赤坂1-4-7
豊川稲荷妙厳寺(愛知県豊川市)の、唯一の直轄別院。
大岡越前守忠相が豊川稲荷から吒枳尼天(商売繁盛の神)を勧請し、屋敷稲荷として自邸で祀った。文
-
な 波除稲荷神社
- [ 神社 | 稲荷 ]

-
中央区築地6-20-37
明暦の大火後、4代将軍家綱公が手がけた築地の埋め立て工事が行われたが、荒波の影響で工事は難航。その最中のあ
-
の 野毛大塚古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
世田谷区野毛1-25
5世紀前半の帆立貝式前方後円墳。
全長82メートル、直径66メートル、高さ11メートルの円墳に小さな前方部が付いた帆立貝式古墳(ほたてがいし
- [ 寺院 ]

-
世田谷区等々力3-15-1
平安時代末期の創建とされる。儒学をはじめ、和歌、兵学武芸、天文測量などを修めた江戸時代の学者細井広沢が眠る
-
み 三囲神社
- [ 神社 ]
-
墨田区向島2-5
境内には雨乞いの句碑が立っている。
元禄6年(1693年)俳人の宝井其角が参拝に訪れた時、日照り困っていた地元の者の哀願によって、この神に雨乞
-
め 明治神宮

- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
渋谷区代々木神園町1-1
JR山手線原宿駅西側に広がる広大な境内地。1920年(大正9)の創建で、明治天皇、昭憲[しょうけん]皇太后
-
や 柳森神社
- [ 神社 ]
-
千代田区神田須田町2-25
長禄2年(1458年)太田道灌が江戸城の鬼門除けとして数多くの柳の木を植えた際に江戸の鎮守として祀られたの
-
よ 与謝野晶子文学碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-
新島村式根島1001
式根港近くにある与謝野晶子文学碑。
1938(昭和13)年に島を訪れた与謝野晶子が詠んだ歌、「波かよふ門をもちたる岩ありぬ式根無人の嶋なりしか
- [ 神社 ]

-
小笠原村父島字東町105
父島の集落のすぐそばにある神社。
父島の中心街を見下ろす山の中腹にある神社。祭りや相撲大会などが催される、島の信仰のよりどころのようです。神
-
か 葛飾区山本亭
- [ 歴史的建造物 ]

-
葛飾区柴又7-19-32
大正15~昭和2(1926~7)年頃の山本栄之助翁邸を改修して公開。
実業家の山本氏の住居が昭和63年3月に葛飾区に移転されたもので、平成3年4月から一般公開されています。大正
- [ 神社 | 自然 ]
-
大島町差木地2
差木地の「岳の平」のふもとにある神社別名「おしずめ様」
銅でできた鳥居は江戸時代中期に造られたもの。境内には都の天然記念物(春日神社のイヌマキ群叢)に指定された樹
-
か 亀有香取神社
- [ 神社 ]

-
葛飾区亀有3-42-24
両さんが清掃をする場面で登場する神社。
鎌倉時代建治二年八月十九日(西暦一二七六年)、当時亀有の地は下総国葛西御厨亀無村と呼ばれ、香取大神宮の神領
- [ 歴史的建造物 ]

-
台東区上野公園8-43
2018年11月2日(金)リニューアルオープン。国の重要文化財に指定されている、日本最古の木造の洋式音楽ホ
-
ご 五條天神社
- [ 神社 ]
-
台東区上野公園4-17
日本三薬祖神のひとつ。
日本武尊が東征のおりに大己貴命と少彦名命を上野忍が岡に祀ったものとされ、天神山(現摺鉢山)や瀬川屋敷(現ア
-
じ ジュリア記念碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-
神津島村ありま
オタア・ジュリアを偲ぶ白亜の大十字架の記念碑。
キリシタン禁教令によって流罪となった韓国女性オタア・ジュリア。彼女の遺徳をたたえ、島民によって1985(昭
-
す 水天宮(中央区)

- [ 神社 | パワースポット ]

-
中央区日本橋蛎殻町2-4-1
江戸時代に、九州・久留米水天宮の分祀としてまつられた。安産と水難除けの神様として厚く信仰されており、女性の
-
と 東岳寺
- [ 寺院 ]
-
足立区伊興本町1-5-16
慶長18年(1614)年浅草鳥越に起立。境内には「東海道五十三次」で有名な絵師、初代安藤広重の墓所がある寺
-
ど 道場寺
- [ 寺院 ]
-
練馬区石神井台1-16-7
文中元年(北朝応安5年、1372年)、当時の石神井城主豊島景村の養子輝時(北条高時の孫)が、大覚禅師を招い
- [ 神社 ]

-
大島町岡田4
毎年1月中旬に行なわれている祭礼の「テコ舞」は、東京都の無形文化財に指定。
祭神は源為朝。御神体は『九重の巻物』で、保元の乱で敗れた為朝が大島に配流された際に奉じて来たといわれる。氏
-
ひ 檜原村郷土資料館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
西多摩郡檜原村3221
檜原村のふるさと再発見の拠点、郷土資料館
遺跡発掘に伴う出土品や昔から使われていた民具や古文書、村に生息している動植物を展示。先史時代からはじまる檜
- [ 神社 | 博物館・資料館 ]

-
文京区本郷5-27-11
たけくらべ、にごりえ、十三夜で知られる樋口一葉ゆかりのお寺。
和順山歓喜院法真寺といい、慶長元年(1596年)に京都知恩院より、寺号を附与されている。家康公御台所の天野
- [ 寺院 | 不動 | 初詣スポット ]

-
目黒区下目黒3-20-26
目黒不動(目黒不動尊)の通称で呼ばれている不動尊。
808年(大同3年)円仁が下野国から比叡山に赴く途中に不動明王を安置して創建した伝わる。古くから浅草の浅草
-
あ 阿伎留神社
- [ 神社 ]
-
あきる野市五日市1081
延喜式神名帳に名を連ねる古社。
関東の鎮守として、源頼朝、足利尊氏、徳川家康などの名将に崇拝されたとつたえられる。大晦日から元旦にかけては