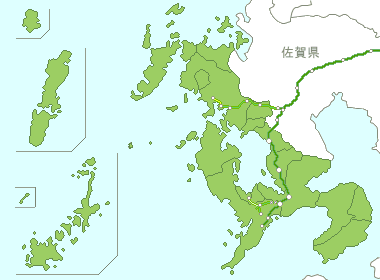神社・寺院・歴史 一覧

-
は 原山支石墓群
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
南島原市北有馬町原山
「原山ドルメン」ともいわれ、日本最大級の支石墓群。
縄文時代晩期の共同墓地で、日本最大級の支石墓群で1972年(昭和47年)11月6日国の史跡に指定。支石墓は
-
は 原城跡
- [ 歴史 | 城 ]

-
南島原市南有馬町大江
天草四郎最後の舞台「原城跡」
別名「日暮城」。原城は島原城の築城によって廃城したものの、その当時起こった島原の乱で天草四郎が率いた一揆軍
-
ひ 冷水教会
- [ 教会 | 歴史的建造物 ]
-
南松浦郡新上五島町網上郷冷水623-2
明治40(1907)年完成の木造建築の教会堂。教会建築の第一人者といわれる鉄川与助が棟梁として初めて設計、
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
平戸市大久保町2477
日本初の洋風建築の石造倉庫を復元。
慶長14(1609)年にオランダ船が入港して以来、およそ33年にわたってオランダ貿易の拠点として栄えた場所
-
ひ 東山手甲十三番館
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
長崎市東山手町3-1
明治中期に外国人居留地に建築された木造2階建て洋館。
活水女子大学そばのオランダ坂沿いの洋館。明治27(1894)年ころに建てられた賃貸住宅で、イギリス人、アメ
-
ふ 福江武家屋敷通り
- [ 道・通り・街 | 歴史 ]
-
五島市武家屋敷
仲町と南町を結ぶ通りは武家屋敷通りと呼ばれ、当時の面影が色濃く残る風情豊かな通り。五島藩主第22代五島盛利
-
お 大浦教会
- [ 教会 ]

-
長崎市南山手町2-18
長崎大司教区が大浦天主堂の隣接地に建立した教会
国宝大浦天主堂が、観光客の増加に伴い、司牧のためには不都合となってきたため、昭和50年(1975)11月、
-
お 男獄神社
- [ 神社 | 珍スポット ]
-
壱岐市芦辺町箱崎本村触
標高約150mの深く険しい男岳山頂にある神社。
昔は、牛を奉納していたが、現在は200体以上の石猿が並ぶ。この地区で習慣がある子孫繁栄、商売繁盛などを願っ
-
か 勝本城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
壱岐市勝本町坂本触城ノ越757
豊臣秀吉の秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)に際して急造された武末城の城跡公園。現在は石垣の遺が残るのみ。展望台か
-
か 頭ヶ島教会
- [ 教会 | 歴史的建造物 | 珍スポット ]

-
南松浦郡新上五島町
西日本唯一の石造り教会「頭ヶ島教会」
隠れキリシタンとして島に住んでいた信者たちが島内産の石を切り出し、積み上げて造ったといわれる全国でもめずら
-
し 島原城

- [ 城 | 歴史 ]

-
島原市城内1-1183-1
別名、森岳城、高来城。
寛永元年(1624年)、築城の名手と讃えられた藩主・松倉重政が、7年の歳月をかけて完成させた城。この時領民
-
ど 堂崎天主堂
- [ 教会 | 歴史的建造物 ]

-
五島市奥浦町2019
禁教令が解かれた後の五島における最初の教会として設立。
赤レンガが印象的な天主堂で、堂内はキリシタン資料館となっていてる。明治12年(1879年)に建てられ、五島
-
ほ 方倉神社
- [ 神社 ]
-
平戸市生月町壱部2739
生月の方では「方倉さん」と呼ばれている方倉神社。
古くから生月の守り神として信仰されてきた神社。水天宮ともいいその昔九十九匹の河童が住み着いたと言う伝説があ
-
あ 天岩戸神社
- [ 神社 ]
-
西臼杵郡高千穂町岩戸1073番地1
岩戸川を挟んで東本宮と西本宮がある。戸川対岸の断崖中腹にある「天岩戸」と呼ばれる岩窟(跡)を神体とする。西
-
あ 安国寺
- [ 寺院 ]
-
壱岐市芦辺町深江栄触546
足利尊氏・直義兄弟が暦応年間(1338~42)に全国60余州に建てた安国禅寺の一つに数えられる。仏殿の床が
-
い 岩戸神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
雲仙市瑞穂町西郷丁2322
古くから「岩戸さん」の愛称で地元の人々に親しまれている神社
縄文人が住んでいたと言われている洞窟が御神体。水源の森に静かに佇む。
-
い 井持浦教会
- [ 教会 | 歴史的建造物 ]

-
五島市玉之浦町玉之浦1243
明治28年(1895年)にフランス人宣教師ペルー神父によって建てられたロマネスク様式の教会。ここには、聖母
- [ 教会 ]

-
佐世保市三浦町4-25
佐世保駅すぐそばの小高い丘に立つ教会。
白い尖塔をもつゴシック様式で昭和5年(1930年)に建てられた。第二次世界大戦中は、空襲の目標となるのを避
-
さ 坂本国際墓地
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
長崎市坂本1
明治21年に設けられた外人向け墓地。トーマス・グラバー夫妻、永井隆博士夫妻などの墓がある。
山王通りから山手に入った場所にある外人向け墓地。南側の入り口付近には、原爆で被爆しながらも医療活動を続けら
-
す 主藤家住宅
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
対馬市厳原町豆酘2752
19世紀中頃に建てられた対馬の家格の高い農家家屋。
土間他に、だいどころ(居間)、ほんざ(座敷)、なんど(寝室)からなる間取りで、二方に縁を設けた対馬独特の構
-
す 住吉神社 壱岐市
- [ 神社 ]
-
壱岐市芦辺町住吉東触
名神大社に列せられた古社で、岩戸神楽が有名。
「日本初の住吉神社」を称し、長門国・摂津国・筑前国の住吉神社と共に「日本4住吉」の一つに数えられ、神功皇后
-
た 橘神社
- [ 神社 | 初詣スポット | 桜 ]
-
雲仙市千々石町己529
昭和15年(1940年)創建の、明治時代の軍人・橘中佐を祀る神社。
国道57号に面して九州一のみかげ石の大鳥居や年末になるとギネスブックにも認定された「世界一の門松」が登場し
-
て 天祐寺
- [ 寺院 | 紅葉 ]
-
諫早市西小路町1116
諫早家の菩提寺で、西郷尚喜の開基。
室町末期の領主・西郷尚が菩堤寺として開いた曹洞宗の寺。のちに諫早氏の菩堤寺となる。境内には、初代龍造寺家晴
-
は 畑ノ原窯跡
- [ 歴史 ]
-
東彼杵郡波佐見町村木郷1343
慶長年間(1596~1614)に李朝の陶工によって築窯されたと伝えられる窯跡。
慶長年間(1596~1615年)の築窯と推定されるもので、国の史跡。波佐見町最古の窯跡の一つとされる。発掘
- [ 歴史 | 公園 ]
-
南島原市有家町尾上5632
町内で発見されたキリシタン墓碑21基が合祀されている。
昭和62年、島原の乱後350年忌の記念事業として設置された西洋墓地風の公園。台付きのカルワリオ十字文、花十
-
き 吉利支丹墓碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
南島原市西有家町須川東向共同墓地内
ローマ字文が刻まれた墓碑として日本最古とされる蒲鉾型の墓碑。
最も美しい形といわれる反円柱蓋石型。碑の背面に薬研彫された大きな花十字紋(碑文は日本最古のローマ字金石文)
-
く 黒島天主堂
- [ 教会 ]
-
佐世保市黒島町3333
黒島にあるカトリック教会の聖堂。
江戸時代の迫害を逃れて移住してきた隠れキリシタンが多く住んでいた黒島。島の中央に建つ黒島天主堂は、明治35
-
こ 興福寺(長崎市)
- [ 寺院 | 歴史 ]

-
長崎市寺町4-32
黄檗宗の開祖隠元禅師ゆかりの日本最古の唐寺。
元和6(1620)年建立の日本最古の唐寺。山門が朱塗りであるため、あか寺とも呼ばれる。崇福寺・福済寺ととも
-
し 聖福寺
- [ 寺院 | 歴史 ]
-
長崎市玉園町3-77
「長崎四福寺」とよばれる黄檗宗の由緒あるお寺。
聖福寺は延宝5年(1677)、京都宇治の黄檗山万福寺の末寺として鉄心禅師が創建した黄檗宗の唐寺。興福寺、崇
-
た 高島秋帆旧宅
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
長崎市東小島町5-38
荻野流砲術および西洋砲術の研究をした、兵学者・高島秋帆の邸宅跡。
幕末の砲術家として知られる高島秋帆の住居跡。高島家は長崎の町年寄を務めた旧家。跡地は国の史跡指定後、原爆に