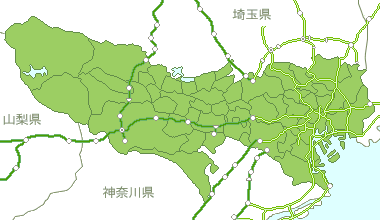神社・寺院・歴史 一覧

- [ 寺院 | 不動 ]
-
豊島区高田2丁目12番39号
江戸三大不動・江戸五色不動のひとつ、目白不動尊を祀っていることで知られている。開基である僧・永順が本尊であ
-
さ 三光院
- [ 寺院 ]
-
小金井市本町3-1-36
座禅教室、精進料理など身近なところから、禅宗にふれられる。
昭和9年、京都嵯峨野の曇華院から招かれた米田租栄禅尼により開山された臨済宗の尼寺。竹乃御所流精進料理が3コ
-
し 島酒之碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-
八丈町大賀郷
島酒醸造用の大甕を碑に使用している。
八丈島に芋焼酎の製法を伝えた丹宗庄右衛門翁の徳を誉めたたえるとともに、芳醇な島酒を讃えるために1967年に
-
せ 世田谷八幡宮
- [ 神社 ]
-
世田谷区宮坂1-26-3
寛治五年(1091年)後三年の役(1083~87)の帰途、源義家がこの宮の坂の地で豪雨に会い、天候回復を待
-
せ 石田寺
- [ 寺院 ]
-
日野市石田1-1-10
土方歳三の魂が眠る寺
宗派は真言宗、愛宕山地蔵院石田寺。高幡山金剛寺の末寺です。古くからこの地に土着していた土方一族の墓所で、境
-
つ 佃島渡船の碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
中央区佃1-11-4(佃公園内)、湊3-18(佃大橋橋詰)
正保2(1645)年から昭和39(1964)年まで続いた渡船(佃の渡し)の石碑。昭和2(1927)年3月に
- [ 寺院 | 碑・像・塚・石仏群 ]
-
豊島区巣鴨3-35-2
本尊は地蔵菩薩(延命地蔵)。とげぬき地蔵の通称で知られる。
慶長元年(1596年)、扶岳太助が江戸神田湯島に創建。1891年(明治24年)、巣鴨に移転。1945年(昭
-
の 野毛大塚古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
世田谷区野毛1-25
5世紀前半の帆立貝式前方後円墳。
全長82メートル、直径66メートル、高さ11メートルの円墳に小さな前方部が付いた帆立貝式古墳(ほたてがいし
-
は 花の碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
台東区浅草7-1 隅田公園内
浅草側の隅田公園内にある歌碑。
作詞・武島羽衣、作曲・滝廉太郎の時代を超えて歌い続けられている名曲の歌碑。
-
は 花園稲荷神社
- [ 神社 | 稲荷 ]

-
台東区上野公園4-17
倉稲魂命(うがのみたまのみこと=豊受姫命:とようけひめのみこと)縁結び・商売繁盛創祀不祥。承応3年(165
- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット | 祭り・イベント ]

-
千代田区永田町2-10-5
皇城の鎮・東都鎮護の社。室町時代の武将太田道灌が江戸城築城にあたり、守り神として創設した。毎年6月15日前
-
ま まいまいず井戸
- [ 歴史 | その他 ]
-
羽村市五ノ神1-1
鎌倉時代に造られたと推定される井戸。
直径16m、深さ4mの井戸で五ノ神社の境内にある、かたつむり状の通路をつけて掘りくぼめた井戸で、鎌倉時代に
-
む 武蔵国府跡
- [ 歴史 ]

-
府中市宮町2-5-3
武蔵国(現在の埼玉県・東京都・神奈川県の一部)の国府に関する遺跡。武蔵野台地上に広がり、中心は武蔵国総社「
-
や 谷保天満宮

- [ 神社 | 梅 | 花 ]

-
国立市谷保5209
関東の三大天神のひとつ、谷保天満宮!
東日本最古の天満宮で、亀戸天神社・湯島天満宮と合わせて関東三大天神と呼ばれる。梅園は梅の名所としても知られ
-
あ 穴八幡宮
- [ 神社 | パワースポット ]
-
新宿区西早稲田2-1-11
蟲封じのほか、商売繁盛や出世、開運に利益があるとされている。
康平5(1062)年に鎮座。江戸時代、南側の山裾を切り開いた際に神穴が現れたことから穴八幡宮といわれる。江
-
あ 阿伎留神社
- [ 神社 ]
-
あきる野市五日市1081
延喜式神名帳に名を連ねる古社。
関東の鎮守として、源頼朝、足利尊氏、徳川家康などの名将に崇拝されたとつたえられる。大晦日から元旦にかけては
-
い 石浜神社
- [ 神社 ]

-
荒川区南千住3-28-58
浅草名所七福神、寿老神を祀る。
神亀元年(724)9月11日に聖武天皇の勅願によって鎮座されて以来、約1280年の歴史を持つ神社。境内には
-
い 池上本門寺
- [ 寺院 | 桜 | パワースポット ]

-
大田区池上1-1-1
五重塔は高さ29メートル。空襲による焼失をまぬがれた貴重な古建築の1つ
日蓮上人入滅の地に創建された日蓮宗の大本山。現存する最古で最大の五重塔。加藤清正が寄進した96段の石段を上
-
い 稲根神社
- [ 神社 ]

-
御蔵島村稲根
本殿は里部落から南へ約8Kmほど離れた反対側(通称アカイガワ)に鎭座している。
島の産土神を祀る稲根神社は延喜式にも記録が残る古社で、明治初期の廃仏毀釈令によって、全島民が稲根神社の氏子
-
え 江戸城

- [ 城 ]

-
千代田区千代田
江戸時代には江城(こうじょう)と呼ばれ、別名千代田城(ちよだじょう)とも呼ばれる。徳川家康が江戸城に入城し
-
お 王子神社
- [ 神社 ]

-
北区王子本町1-1-12
元准勅祭・東京十社の北方守護。
源義家の奥州征伐の折、当社の社頭にて慰霊祈願を行い、甲冑を納めた故事も伝えられ、古くから聖地として崇められ
-
お 小河内神社
- [ 神社 ]
-
西多摩郡奥多摩町河内149
首都用水の護り神
小河内貯水池建設の為水没した旧小河内村に祀られていた九社十一祭神を勧請して創建された小河内地区の鎮守神。奥
-
か 葛飾区山本亭
- [ 歴史的建造物 ]

-
葛飾区柴又7-19-32
大正15~昭和2(1926~7)年頃の山本栄之助翁邸を改修して公開。
実業家の山本氏の住居が昭和63年3月に葛飾区に移転されたもので、平成3年4月から一般公開されています。大正
-
か 片倉城跡公園
- [ 歴史 | 公園 ]

-
八王子市片倉町2475
室町時代に築かれた、片倉城の城跡を公園として整備。
水車小屋や二の丸広場があり、市民の憩いの場となっている。花も多く、特に3月下旬のカタクリは有名。6月には菖
-
き 清水観音堂
- [ 観音 ]
-
台東区上野公園1-29
寛永寺を開創した天海が京都清水寺を模して寛永八年(1632)に創建。国の重要文化財に指定されている。境内に
-
こ 光厳寺
- [ 寺院 | 桜 ]
-
あきる野市戸倉328
臨済宗建長寺派鷲峯山(じゅほうさん)光厳寺は建武年間に足利尊氏が創建したと伝えられている寺。北朝の天皇・光
-
こ 国分寺薬師堂
- [ 寺院 ]

-
国分寺市西元町1
国分寺境内にあり、建武2年(1335年)新田義貞の寄進により、現在の金堂跡付近に建立されたとあります。国分
- [ 寺院 ]

-
世田谷区松原5-43-30
京都伏見に創建された古刹。
江戸御坊創建の一年前の元和二(1616)年、玄覚法師(開基)によって京都伏見に「伏見山正法寺」として創建さ
-
し 七人塚
- [ 歴史 ]
-
御蔵島村
謀反を計画した7人が埋葬されている。
宝暦年間(1751~1764)に御蔵島流刑になり島をのっとる企てをした8人の流人。謀反を計画した7人が埋葬
-
じ 浄名院
- [ 寺院 ]
-
台東区上野桜木2-6-4
へちま供養で有名なお寺
寛永寺36坊の一つとしてとして圭海大僧都が開基となり寛文6年(1666)創建、享保8年(1823)に寺号を