神社・寺院・歴史 一覧

- [ 寺院 ]

-
日光市山内2300 日光山輪王寺
徳川家光の発願で建てられた青銅の供養塔。
世界遺産・重要文化財。高さ約15mの塔の上部に24個の金の鈴や葵の御紋が見られ、塔下には1000部の経典が
-
い 岩船山高勝寺
- [ 寺院 | パワースポット ]
-
下都賀郡岩舟町静3
恐山、大山と並ぶ日本三大地蔵のひとつ。
宝亀年間(770~781)に、弘誓坊明願(ぐぜぼうみょうがん)が開いたと伝えられる。かつては死者の霊が集ま
-
さ 西明寺(芳賀郡)
- [ 寺院 ]
-
芳賀郡益子町益子4469
天平年間(729年~749年)行基の開山、紀有麻呂の開基によって創建されたと伝えられる。室町時代に建てられ
-
た 高田山専修寺
- [ 寺院 ]

-
真岡市高田1482
西暦1225年(嘉禄元)に親鸞上人53歳の時、真岡城主大内氏の懇請により建立。長野の善光寺から一光三尊仏を
-
た 田中正造旧宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
佐野市小中町975
生涯、足尾鉱毒事件で闘い続けた田中正造が生まれ育った家。表門、母屋、隠居所、土蔵、便所などが現存。家族が明
-
つ 綱神社
- [ 神社 ]
-
芳賀郡益子町上大羽2350
建久5(1194)年に宇都宮氏の第3代当主宇都宮朝綱が創建した神社。
朝綱が謀反の疑いで土佐に流罪になった際、土佐の加茂明神に祈って罪を許されたことを感謝して、本国に帰った後、
-
へ 平和観音
- [ 観音 | 展望台 ]

-
宇都宮市大谷町
大谷石の採掘場跡に立つ高さ27mの観音像。
世界平和を祈って昭和29年に完成したもの。胸のところには町を一望できる展望台がある。
-
う 宇都宮城址公園
- [ 城 | 公園 ]
-
宇都宮市本丸町、旭1
関東七名城の一つである宇都宮城を復元、宇都宮城址公園として一般に公開。土塁、堀と清明台、富士見櫓、土塀を再
-
お 岡本家住宅長屋門
- [ 歴史的建造物 ]
-
宇都宮市下岡本町1624-1
代々庄屋格組頭を務めた旧家で、正徳4(1714)年以前に建てられた建物は重要文化財に指定。
-
し 史跡足利学校
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
足利市昌平町2338
日本最古の総合大学といわれ、創建は奈良・平安・鎌倉・室町時代と諸説ある。江戸時代の孔子廟と学校門が残るほか
- [ 寺院 | 歴史 ]
![慈眼堂[日光山輪王寺]](../img/dum.png)
-
日光市山内2300
天海大僧正-てんかいだいそうじょう-が眠るところ。
輪王寺に属する二つ堂の常行堂・法華堂の間にある入口を通り抜けると、老杉が立ち並ぶ石畳の急な坂道が現れる。こ
- [ 寺院 ]

-
日光市山内2300 日光山輪王寺・大猷院
霊廟への最初の入り口となる夜叉門。
正面、背面の左右柵内に阿跋摩羅、毘陀羅、背面に烏摩勒伽、けん陀羅の4体が納められ、厄除け、幸運の夜叉として
- [ 教会 ]
-
日光市本町1-6
建築設計家、教育者、宣教師として明治、大正期に足跡を残した米国人ガーディナーが設計し1914年(大正3年)
-
に 日光二荒山神社
- [ 神社 | パワースポット ]

-
日光市山内2307 二荒山神社
下野国の僧・勝道上人が767年(神護景雲元年)二荒山(男体山)の神を祭る祠を建てたことに始まるとされる。
古くより、霊峰二荒山(ふたらさん・男体山)標高2486mを神の鎮まり給う御山として尊崇したことから、「二荒
-
あ 明石弁天
- [ 神社 ]
-
足利市本城2-1805
1793(寛政5)年、足利城址のある両崖山の山麓に創建された古社。清泉が湧く池があったので、水にゆかりの深
-
い 医王寺(鹿沼市)
- [ 寺院 ]
-
鹿沼市北半田1250
天平元年(765)勝道上人によって開山したのが始まりと伝わる。江戸初期に日光東照宮の陽明門を模して建てられ
-
じ 地蔵院
- [ 寺院 ]
-
芳賀郡益子町上大羽945-1
1194年(建久5年)宇都宮城主宇都宮朝綱が建立した阿弥陀堂に始まると伝わる。堂内には花鳥、飛竜などの彩色
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
栃木市大平町西山田898-1
国内最大級の舟形木棺をはじめ郷土の貴重な資料を展示。
下野七回り鏡塚古墳出土品(国指定重要文化財)を中心に展示する歴史民俗資料館と、江戸時代の大庄屋の風格を残す
- [ 神社 ]
-
足利市西宮町3129
足利の七福神の一つとして知られる。
1603(慶長8)年に江戸幕府代官・小林重郎左衛門が領地繁栄のために創建。厄除招福・商売繁盛の神で、秋祭り
-
ば 鑁阿寺
- [ 寺院 | 城 | 初詣スポット | パワースポット ]
-
足利市家富町2220
真言宗大日派の本山。
足利氏第2代の義兼が邸内に持仏堂を建て、大日如来を祀ったのに始まりと伝わる。「足利氏宅跡(鑁阿寺)」(あし
- [ 神社 ]
-
日光市山内2307 二荒山神社
神苑境内、神興舎の前に立つ、唐銅製の高さは2.3mある燈籠。その昔二荒山神社の境内で警備にあたっていた武士
-
み 妙雲寺
- [ 寺院 | 花 ]

-
那須塩原市塩原665
ボタンを始め、四季折々のたくさんの花々が咲く。
寿永年間(1182~85)、平重盛の妹・妙雲禅尼が草庵を結んだ古刹。境内には3000株のボタンが咲くボタン
- [ 神社 | 初詣スポット ]

-
真岡市東郷937
厄払い、縁結びの神様。
健康と縁結びのご利益があるとされる、大国様とえびす様を祀る神社。境内地には「日本一えびす様大前恵比寿神社」
-
お 太平山神社
- [ 神社 | 花 | パワースポット ]

-
栃木市平井町659
平安初期に慈覚大師が淳和天皇の勅額を奉じた神社。
太平山自然公園六角堂前から随神門に至る太平山神社表参道、約1000段の石段両側に西洋あじさいをはじめ、額あ
- [ 寺院 | 観音 | パワースポット ]

-
宇都宮市大谷町1198
石窟仏としては日本最古の作といわれる千手観音(大谷観音)
本尊は千手観音で、坂東三十三箇所第19番札所。大谷寺は大谷石凝灰岩層の洞穴内に堂宇を配する日本屈指の洞窟寺
-
か 門田稲荷神社
- [ 神社 | 稲荷 ]
-
足利市八幡町387 下野國一社八幡宮境内
日本三大縁切り稲荷のひとつ。
下野國一社八幡宮の境内にある神社。縁切りに関する古い絵馬が数多く残る。
- [ 教会 ]

-
宇都宮市松が峰1-1-5
大谷石造りの聖堂が目印の教会
昭和6~7(1931~1932)年にかけて建てられた大谷石で造られたカトリック教会。礼拝堂内部には、本格的
-
さ 斉藤茂吉歌碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
那須塩原市塩原665
歌人で医師である斉藤茂吉の歌碑。「とうとうと喇叭をふけば塩はらの深染の山に馬車入りにけり」が建っている。こ
-
さ 三仏堂
- [ 歴史 | 歴史的建造物 ]

-
日光市山内2300
伽藍全体に朱塗りを配した東日本最大の木造建造物。
輪王寺の本堂(重要文化財)にあたり、重層入母屋造、銅瓦葺、間口33.8m、奥行21.2m、伽藍全体に朱塗り
-
し 下野薬師寺歴史館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
下野市薬師寺1636
下野薬師寺の歴史を紹介する展示施設。下野薬師寺は僧侶に戒律を授ける日本三戒壇のひとつで、古代、東国の僧たち
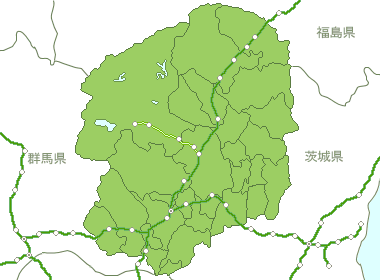




![慈眼堂[日光山輪王寺]](../img_spot/9142_t1_s.jpg?201905062330)








