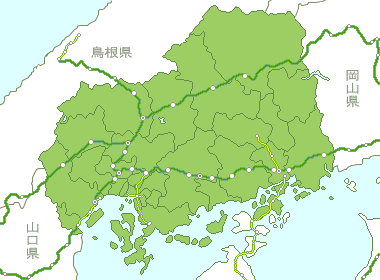神社・寺院・歴史 一覧

-
い 嚴島神社

- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-
廿日市市宮島町1番地
世界文化遺産厳島神社
俗に「安芸の宮島」と呼ばれ、日本三景の一つにもなっている厳島に鎮座する社で、推古天皇即位の6世紀末に創建。
- [ 歴史 | 博物館・資料館 | 科学館 ]

-
呉市宝町5-20
呉の歴史と平和の大切さ,科学技術を学ぶ博物館「大和ミュージアム」
科学技術のすばらしさを体感できる4階建ての大型ミュージアム。明治時代以降の造船の街あるいは軍港・鎮守府とし
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
広島市中区中島町1-2
原爆に関するさまざまな資料で原爆の実態を知ることができる。爆発点の温度は100万度以上、放射線や熱線、爆風
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-
広島市中区中島町
広島平和記念公園内に設置されている慰霊碑。
平和記念公園の中央に立っており、正式名称は広島平和都市記念碑という。原爆犠牲者の霊を雨露から守りたいという
- [ 歴史街道 ]

-
竹原市本町
訪れる人に憧れと懐かしさを抱かせる「憧憬の路」
本川に沿った上市、下市周辺は、江戸後期の町並みをとどめ、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。石畳の
-
ひ 広島城

- [ 城 | 歴史 ]

-
広島市中区基町21-1
天正17年(1589年)、毛利輝元築城の城。
1589年(天正17)に毛利輝元が築城した城。鯉城[りじょう]とも呼ばれる。かつて国宝に指定されていた天守
-
ぶ 佛通寺

- [ 寺院 | 紅葉 ]

-
三原市高坂町許山22
[ 紅葉時期 11月上旬~11月中旬 ]
日本屈指の参禅道場として知られる臨済宗佛通寺派の大本山。室町時代の文化財も多い。秋には赤、黄、朱色など色と
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
尾道市東土堂町8-28
おのみち文学の館の施設の一つ。
「文学記念室」、「中村憲吉旧居」、「志賀直哉旧居」とその建物南側に記念碑がたつ「尾道市文学公園」の4つの施
-
だ 大聖院
- [ 寺院 | 紅葉 | パワースポット ]

-
廿日市市宮島町210
宮島で最古の歴史を持つ寺院。
霊峰・弥山には、弘法大師の足跡を残す遺跡が各所にある。大聖院はそれらを統括する真言宗御室派の大本山。厳島神
- [ 神社 ]

-
廿日市市宮島町1-1
厳島神社にもほど近い「塔の岡」に建てられた巨大建築。
豊臣秀吉の命によって造営が始まったが、慶長3(1598)年の秀吉の死により工事が途中で中止され、板壁も天井
- [ 教会 ]

-
広島市中区幟町4-42
広島で被爆したフーゴー・ラッサール神父が、ローマ法王をはじめ世界中の人々の協力を得て昭和29年8月6日に建
-
げ 原爆の子の像
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-
広島市中区中島町1 平和記念公園内
原爆による白血病で12歳で亡くなった佐々木禎子さんの同級生等による募金運動により作られた像。
原爆の犠牲となった子どもたちを慰霊するため、各地の少年少女たちからの寄付などで建てられた。1958年5月5
- [ 歴史街道 ]
-
竹原市
訪れる人に憧れと懐かしさを抱かせる「憧憬の路」
-
ひ 広島護國神社
- [ 神社 | 初詣スポット ]

-
広島市中区基町21-2
広島城址公園内にある護国神社。
明治元(1868)年、二葉の里に造営された水草霊社に奉祀されたのが創建とされる。原爆で一度焼失したが、昭和
-
わ 若胡子屋跡
- [ 歴史的建造物 ]
-
呉市豊町御手洗
広島藩公認の御茶屋だった建物。
若胡子屋は、多くの遊女をかかえるお茶屋。離れ座敷にある屋久杉の天井板や土塀が当時の華やかさを伝える。江戸時
-
ふ 不動院(広島市)
- [ 寺院 | 不動 | 桜 | 紅葉 ]

-
広島市東区牛田新町3-4-9
14世紀中頃、足利尊氏が全国に建立した安国寺の一つといわれ、のちに禅宗から真言宗に改宗、不動院となった。原
-
た 帝釈天永明寺
- [ 寺院 ]
-
庄原市東城町帝釈未渡
霊峰石雲山の麓、帝釈川の最上部に立つ古刹。
709年(和銅2)行基によって開基と伝えられる。帝釈峡の名の起源となった帝釈天を本尊として安置しています。
-
あ 安芸国分寺
- [ 寺院 ]

-
東広島市西条町吉行2064
741年(天平13)、聖武天皇の詔により建てられた国分寺の一つ。寺の西約50mにかつての国分寺の塔跡があり
-
ら 頼杏坪役宅運壁居
- [ 歴史的建造物 ]
-
三次市三次町1828-2
別名を運壁居。
頼山陽の叔父、杏坪が文政11(1828)年から3年間、町奉行として執務していたところ。書斎や庭など、簡素な
- [ 歴史 | 公園 | 展望台 ]

-
呉市豊町御手洗
重要伝統的建造物群保存地区を見下ろせる高台に設けられた公園。
展望台から御手洗の古い町並みや瀬戸内海の島々、愛媛との県境になる岡村橋やミカンの段々畑が見渡せる。
-
き 旧海軍兵学校
- [ 歴史的建造物 ]

-
江田島市江田島町国有無番地
海を愛した若人たちの熱い思いが息づいている,旧海軍兵学校
構内は明治期のレンガ構造物や大正時代の石造の大講堂、昭和初期の教育参考館など、近代建築の博物館さながら。現
-
ふ 福山城

- [ 城 | 歴史 ]

-
福山市丸之内
伏見櫓、筋鉄御門は、伏見城から移されたもので重要文化財。
1619年(元和5)徳川家康の従兄弟・水野勝成[みずのかつなり]が福山十万石の領主となって築城。天守閣は1
- [ 神社 ]

-
廿日市市宮島町1-1
天正15年(1587年)、豊臣秀吉が戦で亡くなった者への供養として毎月一度千部経を読誦するため政僧・安国寺
-
よ 吉井邸
- [ 歴史的建造物 ]
-
竹原市本町
竹原の町並みで、現存する最古の建築。
屋号を「米屋」といい、代々続いた豪商の家。江戸時代の本陣、棒瓦入母屋、塗りごめ壁、格子窓の建物である。多く
-
ひ 櫃田三十番神
- [ 神社 ]
-
三次市君田町櫃田、田和瀬
番神さんと呼ばれ親しまれています。
君田町櫃田に三十番神を祭る祀が2か所あり、1つは櫃田田和瀬にあるもの、他の1つは櫃田寺原にあるものです。3
- [ 歴史街道 | 歴史 ]

-
呉市豊町御手洗
江戸時代の町並みが今も残る。
御手洗は江戸時代、北前船や幕府の交易船の寄港地として栄え、風待ち潮待ちの港として知られていた。町には、江戸
-
み 御手洗七卿落遺跡
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
呉市豊町御手洗
休憩所・資料館として整備されている。
元治元(1864)年、蛤御門の変で長州軍が幕府に敗れたため、三条実美ら討幕派5人の公卿が、長州兵に守られて
-
は 白雪楼
- [ 歴史的建造物 ]
-
呉市下蒲刈町三之瀬197
多くの漢学者がこの建物を訪れている。
江戸時代に多くの漢学者が集った建物を、明治25(1892)年に頼家9代俊直が竹原市に移築、留春居(りゅうし
-
ぬ 沼名前神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
福山市鞆町後地1225
社伝では今から1800年以上前に創建された格式高い古社。
大綿津見命を主祭神とし、須佐之男命を相殿に祀る海の神様である。地元では「祇園さん」と呼ばれており、京都の八
-
と トンカラリン
- [ 歴史 ]
-
東広島市安芸津町三津信僧
山の畑の段差を利用して作られた石組みの穴。
19世紀頃に造られたと推定される棚田の導水施設。昭和51年に南繁が発見。竪穴と横穴を連結した高さ約75セン