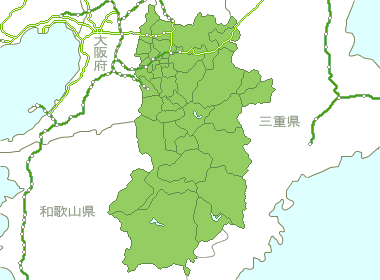神社・寺院・歴史 一覧

-
く 百済寺
- [ 寺院 ]
-
北葛城郡広陵町百済1411-2
聖徳太子が創建した熊凝精舎を継いで、舒明天皇11年(639年)に百済大寺を創建したと伝えられる。本尊は十一
-
へ 平城京歴史館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
奈良市二条大路南4-6-1
中国大陸、朝鮮半島をはじめ大陸との交流により発展した国づくりの歴史や往時の文化・暮らしに焦点を当てたテーマ
- [ 神社 ]
-
奈良市今御門町1
「博打の神さん」として知られている。
祭神は猿田彦命(さるたひこのみこと)と市寸島姫命(いちきしまひめのみこと)境内の巨石は、宝の神として勝負事
-
し 正暦寺
- [ 寺院 | 紅葉 ]

-
奈良市菩提山町157
奈良屈指の紅葉の名所として知られる。
正暦3年(992年)、一条天皇の発願により、関白藤原兼家の子兼俊僧正が創建の名刹。菩提山真言宗の本山(単立
-
め 面不動鍾乳洞
- [ 不動 | 自然 | 自然地形 ]
-
吉野郡天川村洞川
天然記念物に指定されている全長約150mの鍾乳洞。
関西最大クラスの規模を誇り、県の文化財にも指定される名所。鍾乳石を楽しめる数少ない鍾乳洞の1つ、最深部には
-
こ 子嶋寺
- [ 寺院 ]
-
高市郡高取町観覚寺544
753(天平勝宝4)年、孝謙天皇の勅願によって創建と伝わる。
「清水の舞台」で知られる京都東山の清水寺は子嶋寺の僧・延鎮によって開かれたとされ、平安時代中期以降は真言宗
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
高市郡明日香村平田538
飛鳥歴史公園内にある歴史公園館。
国営飛鳥歴史公園4地区の施設や催し物の案内をはじめ、飛鳥地方の史跡や歴史を立体模型や映像を用いて紹介。立体
-
い 糸井神社
- [ 神社 ]
-
磯城郡川西町結崎68
約千年前の「延喜式」書物に糸井社として記されている由緒ある古社。
祭神は豊鋤入姫命(とよすきいりひめのみこと)といわれるが、境内の説明板には綾羽、呉羽の織物の主神とし、江戸
-
と 栃尾観音堂
- [ 観音 ]
-
吉野郡天川村栃尾
1675(延宝3)年、この地を訪れた円空が、栃尾の集落の小さな祠にこもって彫ったといわれる円空仏4体を安置
-
け 牽牛子塚古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
高市郡明日香村越
石槨は巨大な岩をくり抜いて造られている終末期古墳。
発掘調査により、八角墳(八角形墳)であることが判明し、飛鳥時代の女帝で天智天皇と天武天皇の母とされる斉明天
-
と 東大寺 指図堂
- [ 寺院 ]

-
奈良市雑司町406
大仏殿の西にある。法然の画像を祀る堂で、建物は江戸時代末期のものである。鎌倉時代、大仏の復興に携わった俊乗
-
び 白毫寺(奈良市)
- [ 寺院 | 花 ]
-
奈良市白毫寺町392
開基(創立者)は勤操(ごんそう)と伝える。
境内から奈良盆地が一望できる景勝地に建つ寺。本尊は阿弥陀如来。天智天皇の皇子、志貴親王の離宮跡といわれ、阿
-
り 龍泉寺
- [ 寺院 ]
-
吉野郡天川村洞川494
700年頃役行者が泉を発見し、八大龍王を祀ったのが始まりとされる。
吉野の竹林院、桜本坊、喜蔵院、東南院と共に山上ヶ岳にある大峯山寺の護持院の1つ。本尊は弥勒菩薩。近畿三十六
-
い 率川神社
- [ 神社 ]
-
奈良市本子守町18
593年創建の奈良市内最古の神社。
奈良市最古の神社といわれる大神神社の摂社。正式名称は率川坐大神御子神社。別名「子守明神」とも呼ばれている。
-
き キトラ古墳
- [ 歴史 ]

-
高市郡明日香村阿部山136-1
中国蘇州の淳祐天文図より500年古く、世界最古の天文図と判明。
7世紀末から8世紀初めにつくられたと見られる古墳で、石室内から極彩色の四神図壁画発見された。天井には精巧な
-
み 三吉石塚古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
北葛城郡広陵町三吉
馬見丘陵公園の一角に位置する全長45m、直径41.4m、高さ6.5mの古墳。
新木山古墳の西に築かれた東向きの帆立貝式古墳。周囲に馬蹄形の周濠が掘られ、さらに外堤を含めた全長は62mに
-
よ 与楽寺
- [ 寺院 ]
-
北葛城郡広陵町広瀬797
三間四方の四注造本瓦葺の本堂に弘法大師像がまつられている。
四注造本瓦葺きの本堂に、1373(応安6)年に僧行盛が作ったといわれる弘法大師坐像(在銘空海像としては奈良
-
と 東大寺 二月堂
- [ 寺院 ]

-
奈良市雑司町406-1
奈良時代(8世紀)創建の仏堂。
現存する建物は1669年の再建で、日本の国宝に指定されている。奈良の早春の風物詩である「お水取り」の行事が
-
ひ 廣瀬神社
- [ 神社 ]
-
北葛城郡河合町川合99
674年創建と伝わる旧官幣大社。
農耕・治水の神として信仰されてきた若宇加能売命(わかうかのめのみこと)を祀っている。毎年2月11日には全国
-
ぶ 仏隆寺
- [ 寺院 | 桜 ]
-
宇陀市榛原区赤埴1684
室生寺の南門として、空海の高弟、賢恵が創建したとされる古刹。
真言宗室生寺派の寺院で本尊は十一面観音。平安時代前期の嘉祥3年(850年)に空海(弘法大師)の高弟・堅恵(
-
お 岡寺龍蓋寺
- [ 寺院 ]
-
高市郡明日香村岡806
663(天智2)年、義淵僧正の創建したと伝わる。
本尊は厄除け観音として信仰を集めている如意輪観音坐像で、塑像としては日本最大のもの。江戸時代までは興福寺の
-
お おふさ観音
- [ 観音 | 花 ]
-
橿原市小房町6-22
バラが境内に所狭しとあふれる寺院として知られている。
18世紀後半の天明年間に妙円尼が開基したと伝えられる。イングリッシュローズを中心に約1800種およそ200
- [ 神社 ]
-
高市郡明日香村小原
藤原鎌足の生誕地との伝承がある場所に鎮座。
祭神は天照大神、品陀別命、天児屋根命。鎌足が産湯を使ったという井戸が残る。
- [ 神社 | パワースポット ]
-
吉野郡吉野町吉野山1292
吉野山の地主神である金山毘古命(かなやまひこのみこと)を祀る。
境内がユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の一部として登録。中世以降は修験道の修行の場となる。境内
-
く 久米寺
- [ 寺院 | 花 ]
-
橿原市久米町502
大和七福八宝めぐりのひとつ。
7世紀後半、聖徳太子の弟の来目皇子(くめのおうじ)と開基伝わり、弘法大師の大日経感得の地でもある。娘のふく
-
ほ 法隆寺 細殿
- [ 寺院 ]

-
生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1
綱封蔵の北側に細殿、細殿と軒を接して食堂が並んでます。
-
お 音村家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
橿原市今井町1-10-13
屋号を「細九」と称する金物問屋。
初期の町家の面影を残す。主屋の西北隅に、二間続きの「つのざしき」など、随時増築されていた。国の重要文化財。
-
も 本薬師寺跡
- [ 寺院 | 歴史 ]
-
橿原市城殿町
天武天皇が皇后の病気平癒祈願のために建て、698(文武天皇2)年に完成したと伝えられる。平城京遷都の際に移
-
り 龍華山永慶寺
- [ 寺院 ]
-
大和郡山市永慶寺町5-76
柳沢家の菩堤寺。
将軍徳川綱吉の側用人である柳沢吉保が、萬福寺八代住持の悦峯道章を招聘し創建。瓦屋根の山門は旧郡山城の南門を
-
こ 荒神社
- [ 神社 | 日の出 ]
-
吉野郡野迫川村池津川347
荒神岳の頂上(1260m)にある高野山の奥社。
弘法大師も修行した古い社であり、火の神として知られている。三宝大荒神のひとつとして高野山信奉者のほか、全国