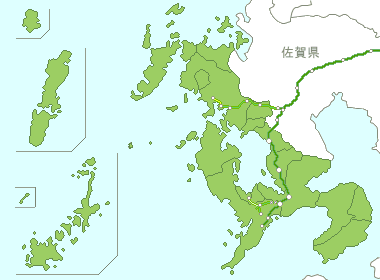神社・寺院・歴史 一覧

- [ 歴史 ]

-
長崎市西坂町7-8
26聖人が1597年(慶長元)に処刑された場所。
長崎市街を見下ろす西坂公園にある。豊臣秀吉によるキリシタン禁止令により、1597年2月5日京阪地方へ伝導し
-
も 桃渓橋
- [ 歴史的建造物 | 橋 ]
-
長崎市出来大工町
昭和60年に復元された桃渓橋。
住民の困惑を見かねた僧卜意が延宝7(1679)年に架設させたもので、架橋当時、河畔に桃の木があったことから
-
り 龍馬通り
- [ 歴史街道 | 歴史 B級スポット ]
-
長崎市寺町
本龍馬をはじめ幕末の若き志士たちが往来した坂道。
長崎市寺町通りの禅林寺と深崇寺にはさまれた路地(長崎市寺町)から、亀山社中跡(亀山社中記念館)を経て風頭公
-
い 生月大魚籃観音
- [ 観音 B級スポット ]
-
平戸市生月町山田免570-1
ブロンズ像としては日本一の大きさです。
生月大橋から見える舘浦の小高い丘にそびえる大魚籃観音(生月観音堂‎)。ブロンズ像では日本屈指の
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
長崎市南山手町8-1 グラバー園内
旧ウォーカー邸の向い側にある旧長崎地方裁判所長官舎。
明治16(1883)年に長崎上等裁判所長、長崎地方裁判所長の官舎として、唯一、居留地以外の長崎市内に建てら
-
と 唐人屋敷跡
- [ 歴史 ]

-
長崎市館内町
密貿易などを防ぐ目的で作られた中国人(唐人)居留地。
元禄2年(1689年)、江戸幕府が密貿易を防ぐことなどを目的として、唐人を集め、住まわせた屋敷跡地。唐館と
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
大村市今富町586-1
大村市郊外にあるキリシタンの墓碑。
大村藩主純忠とともに洗礼を受けた重臣、一瀬越智相模栄正(おちさがみえしょう)の墓碑で、戒名が刻んであります
- [ 教会 | 歴史的建造物 | デート ]

-
平戸市紐差町1039
巨額の工費をかけて建てられた東洋でも屈指のロマネスク様式の大天主堂。
昭和4年(1929年)の建設当時は日本一大きな天主堂だった。仏教の寺院風に造られた屋根は、和洋折衷の不思議
-
さ 崎方公園
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 | 展望台 | 桜 | 花 ]
-
平戸市大久保町遠見2529
平戸の中心街の街並みが一望でき、桜と平戸つつじの名所。
桜と平戸ツツジの名所としても有名な公園。平戸港が一望できる展望デッキがあり、夜はライトアップされる。フラン
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
対馬市厳原町今屋敷668-1
朝鮮との交易が盛んだった対馬の歴史にふれることができる。考古・民俗・歴史資料約100点と対馬に棲むツシマヤ
-
な 長与専斎旧宅
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
大村市久原2-1030-1
長与専斎の旧宅市指定史跡
初代衛生局長として近代医学の基礎を築き、「衛生」の用語をつくったことで有名有名長与専斎の旧宅。当時は片町の
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-
大村市古町1-63
大村藩歴代藩主墓碑群。
日蓮宗本経寺の境内南側の2000坪の敷地に藩主をはじめ、正室・側室・一族家臣など全78基の墓と、石灯籠48
- [ 歴史的建造物 | 歴史街道 ]
-
長崎市南山手町4-33
国の重要伝統的建造物群保存地区に設置されている資料センター。
英国人ウィルソン・ウオーカーが建てた質の高い住宅で、1階・2階とも正面に中央部が突出したベランダを設け、ベ
-
い 壱岐文化村
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
壱岐市郷ノ浦町片原触410
江戸時代からの民具を集めた民芸美術館。
民芸美術品や失われてしまった暮らしの中の道具など、壱岐の昔の暮らしを実感できる。隣接して湯川温泉・壱州本陣
-
し 清水山城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
対馬市厳原町西里
厳原の西に位置する清水山の頂上から、断続的におよそ500mにわたって石塁が残る。一の丸・二の丸・三の丸の石
-
し 島原復興アリーナ
- [ 碑・像・塚・石仏群 | アウトドア ]
-
島原市平成町2-1
長崎県下最大のフロアスペース(62m×43m)を持つ多目的複合施設。
多彩なイベントに対応する多目的複合施設の島原復興アリーナ。敷地内には平成22年のサッカーワールドカップの際
-
あ 淡島神社
- [ 神社 | 桜 | パワースポット | 珍スポット B級スポット ]
-
雲仙市南高来郡国見町神代西里
神代西里地区にあり、縁結び、安産、子育てに霊験があるとされる。
文化9年(1812年)神代藩主10代鍋島茂體公の時代に、亀川出羽守忠英という人によって建立されました。淡島
-
か 釜蓋城跡
- [ 城 | 歴史 | 展望台 ]
-
雲仙市千々石町己 橘公園内
頂には天守閣を模した展望所が建てられている。
天正遺欧使節の一人である千々石ミゲルの父、千々石淡路守が築いた城の跡。城跡は公園として整備されており、グラ
- [ 博物館・資料館 | 歴史的建造物 ]

-
長崎市松が枝町4-27
明治37年(1904年)に建てられた洋館(重要文化財)で、レンガと石造りの3階建て、市内の洋館の中でも最大
-
こ 晧台寺
- [ 寺院 | 初詣スポット ]

-
長崎市寺町1-1
正式には海雲山普昭晧台禅寺という。
江戸初期に建立された曹洞宗の寺で、修行僧がいる専門道場でもある。長崎市内外に末寺が14ヶ寺ある。毎週土曜の
- [ 神社 | パワースポット ]
-
壱岐市芦辺町国分東触464
伝統と格式を誇る式内社
古事記では伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)が天照大神の次に産んだのが月読尊(
-
か カステラ神社
- [ 神社 ]
-
長崎市南山手町1-18 ANAクラウンプラザホテル 長崎グラバーヒル 3F
長崎の名物カステラを祀ってある神社?
グラバー園に向かう手前にある神社。カステラの姿をしたカステラ様を神体にすえている。カステラ様の表情は何とも
-
た 田平教会
- [ 教会 ]
-
平戸市田平町小手田免19
成赤レンガ造りのムードある教会。
平戸瀬戸を見下ろす高台に建つ教会。最初の教会は1888(明治21)年に竣工。その後、信徒の浄財と労働、フラ
-
つ 対馬藩お船江跡
- [ 歴史 ]
-
対馬市厳原町久田
江戸時代、対馬藩が久田川の河口に藩船を格納するために構築した船着き場跡。満潮時には木造の大船が出入できる程
-
ひ 東山手甲十三番館
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]

-
長崎市東山手町3-1
明治中期に外国人居留地に建築された木造2階建て洋館。
活水女子大学そばのオランダ坂沿いの洋館。明治27(1894)年ころに建てられた賃貸住宅で、イギリス人、アメ
-
ぶ 武家屋敷・島原市
- [ 歴史的建造物 ]
-
島原市下の丁
城下町の面影を色濃くとどめる武家屋敷。
一般公開されているのは、山本邸、篠塚邸、鳥田邸の3つ。内部は当時の衣装を身に着けた武士の人形などを置いてい
-
わ 和多都美神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
対馬市豊玉町仁位55-1
海の女神・豊玉姫を祭る古社。
海幸山幸の神話で有名な彦火火出見尊と豊玉姫命を祀る神社。海の守護神として信仰を集めるところで、本殿正面の5
-
う 上野彦馬宅跡
- [ 歴史 ]
-
長崎市伊勢町4-14
彦馬はここで坂本龍馬を撮影したといわれる。
日本初のプロカメラマンとして知られる上野彦馬。この場所は、文久2(1862)年に創設した上野撮影局があった
-
か 頭ヶ島教会
- [ 教会 | 歴史的建造物 | 珍スポット ]

-
南松浦郡新上五島町
西日本唯一の石造り教会「頭ヶ島教会」
隠れキリシタンとして島に住んでいた信者たちが島内産の石を切り出し、積み上げて造ったといわれる全国でもめずら
-
こ 江東寺
- [ 寺院 ]
-
島原市中堀町42
島原城築城主松倉重政の菩提寺。
1558(永禄元)年に創建された禅寺。日本最大ともいわれる涅槃像は境内の墓地にあり、全長約8.1m、高さ約