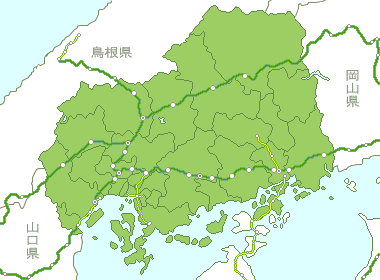神社・寺院・歴史 一覧

-
よ 吉原家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
尾道市向島町樫原
日本最古の「農家」として国の重要文化財に登録。
寛永12(1635)年に建てられた寄棟造のかやぶき屋根の民家で、建築された年が明らかになっている農家の中で
-
お 大元神社
- [ 神社 ]
-
廿日市市宮島町大元公園
大元公園の入口にある神社。
厳島神社創建者の佐伯鞍職を相殿に祀る。六枚重三段葺という現存する建物の中では唯一の板葺屋根が特徴となってい
- [ 寺院 | 桜 | 乗り物 ]
-
尾道市東土堂町20-1
千光寺山の麓から山頂まで結ぶロープウェイ。
市街地より尾道を代表する観光スポット「千光寺公園」まで3分間で結ぶ。女性ガイドが毎回ゴンドラに乗り込んで肉
-
ち 千葉家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
安芸郡海田町中店8-31
屋敷のつくりや庭のたたずまいに当時の様子がうかがえる。
江戸時代に代々広島藩の天下送り役を務めていた千葉家(神保屋)は、酒造業も営む商家だった。本座敷は数寄屋風書
-
こ 光明坊光明三昧院
- [ 寺院 ]

-
尾道市瀬戸田町御寺757
聖武天皇が行基に命じて建立したとされる真言宗の古刹。
天平年間に聖武天皇の勅願で行基が創建した真言宗の寺。本尊の阿弥陀如来坐像や鎌倉時代建立の十三重石塔婆は国の
-
み 三瀧寺
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 ]
-
広島市西区三滝山411
三滝山(宗箇山)の中腹にある高野山真言宗の寺院。
中国三十三観音の第十三番札所や広島新四国八十八ヶ所霊場第十五番札所で、桜や紅葉の名所としても知られる。境内
-
お 太田家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
福山市鞆町鞆842
18世紀中期に建てられた主屋や醸造蔵
元は福山藩の御用名酒屋を務めた保命酒の蔵元「中村家」の屋敷で、明治時代に太田家の所有となった。瀬戸内海の近
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 自然 ]
-
尾道市因島椋浦町
一の城の土居屋敷があった所と伝える。
北麓の城見屋敷が小早川氏の居館と伝えられ、蒲刈小早川栄城の石碑とともに五輪塔群が残っている。
-
じ 浄土寺(尾道市)
- [ 寺院 | 初詣スポット ]
-
尾道市東久保町20-28
聖徳太子が開いたとも伝えられる。
足利尊氏が戦勝祈願に立ち寄ったとして知られる寺。本尊は十一面観音で、中国三十三観音霊場第九番札所。山門と阿
-
か 海龍寺
- [ 寺院 ]
-
尾道市東久保町22-8
鎌倉時代には浄土寺の曼陀羅堂と呼ばれた真言宗の寺。
尾道の古寺巡り最東の寺。真言宗の寺で、本尊は鎌倉時代に造られた千手観音菩薩像(県重要文化財)。境内には江戸
-
こ 古保利薬師収蔵庫
- [ 歴史 ]

-
山県郡北広島町古保利224
平安初期の薬師如来など十二躯の仏像(国の重要文化財)を収蔵。
弘仁年間(810~824年)に弘法大師が自ら仏像を刻み、寺院を建立したと伝えられている。収蔵庫には本尊薬師
-
く 首無地蔵菩薩
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
府中市出口町250
月例大祭には沢山の露店が出店する。
備後の国、広島県東部の府中市出口(でぐち)町の小高い丘に祀(まつ)られている首から上が欠けた石のお地蔵様。
- [ 寺院 | 花 ]
-
府中市栗柄町2987
神宮寺、南宮神社の参道の途中にある寺。
かつての南宮神社の一部だった寺。約80種、3000株のアジサイが見事なことから別名「アジサイ寺」とも呼ばれ
-
こ 光明寺(尾道市)
- [ 寺院 ]
-
尾道市東土堂町2-8
備後路の古刹、瀬戸内水軍ゆかりの寺。
京都東山にあるもみじで有名な浄土宗西山禅林寺派の総本山、永観堂禅林寺の末寺。浄土宗の寺で第12代横綱陣幕久
-
び 備後安国寺
- [ 寺院 | 庭園 ]
-
福山市鞆町後地990-1
釈迦堂は国の重要文化財に指定。
文永10年(1273年)に建立された臨済宗妙心寺派の禅寺。釈迦堂と堂内の本阿弥陀三尊像などは重要文化財に指
-
だ 大慈寺
- [ 紅葉 | 寺院 ]
-
三次市吉舎町吉舎1094
 [ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]
[ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]十三身像観音堂(円通閣)は県重文。
大慈寺は吉舎東方山中にあり,応永28年(1421)に和知信濃守氏実によって開かれた禅宗寺院。
-
あ 阿伏兎観音
- [ 観音 ]
-
福山市沼隈町能登原1427-1
毛利輝元によって創建されたもの。
朱塗りの観音堂は国指定の重要文化財。境内の前はすぐ海になっていて、白壁の外側を波が洗う。志賀直哉の作品『暗
-
あ 安芸國分寺
- [ 寺院 ]
-
東広島市西条町吉行2064
聖武天皇の命により建立された国分寺の一つ。
奈良時代(741年)、聖武天皇の勅命によって、全国60余ヵ国に国分寺が建立され、古代安芸国では当地に建立。
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
尾道市久保1-14-1
尾道の歴史に関する資料を扱った博物館。
尾道市の重要文化財である1923年(大正12年)に建設された尾道銀行本店を改装した博物館。鉄筋コンクリート
-
い 因島水軍城
- [ 歴史 | 城 ]
-
尾道市因島中庄町3228-2
1589(天正17)年、戦国武将の毛利輝元が築いた城。
天守閣は1945(昭和20)年に原爆によって全壊したが、昭和58(1983)年に歴史家、奈良本辰也氏の監修
-
し 白壁の町並み
- [ 歴史街道 ]
-
府中市上下町上下
ロマン溢れる懐かしい町並み。
江戸時代は幕府の天領地であり、また石見銀山からの銀を運ぶ銀山街道の中継地点として栄えていた「上下」。現在の
-
た 対潮楼
- [ 寺院 ]
-
福山市鞆町鞆2
福禅寺の客殿として元禄年間に建てられたもの。
対潮楼は江戸時代の元禄年間(1690年頃)に建立された福禅寺の客殿。江戸時代を通じて朝鮮通信使のための迎賓
- [ 歴史的建造物 ]
-
三次市三良坂町灰塚8-1
江戸末期の建築、木村家住宅を移築し公開。
草茸きの簡素な造りで、母屋の現状は、ウチニワ、オモテ、デイ、ナンド、ダイドコロの部屋を配しています。現在は
- [ 歴史 ]

-
広島市中区中島町1
核の廃絶と平和を目指し、その精神文化運動の象徴として建立された鐘。鐘には、国境のない世界地図が刻印されてい
-
こ 幸運仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 | デート ]
-
神石郡神石高原町下豊松
幸せを運んでくれる「幸運仏様」
道拡張工事の際、地下約1.5kmから2基の五輪塔が掘り出され、仲良く並んでいたことから夫婦墓として供養され
-
げ 原爆ドーム

- [ 歴史的建造物 ]

-
広島市中区大手町
昭和20年8月6日の原爆の実状を伝えるため永久保存されている。
当時の惨状を伝える姿で、太田川の支流、元安川沿いに建ち、戦争の悲惨さを伝えている。世界遺産に登録されている
-
て 天寧寺
- [ 寺院 | 桜 | 花 ]
-
尾道市東土堂町17-29
貞治6(1367)年、足利義詮が創建した寺。
国の重要文化財の塔「海雲塔」があり、本堂左手の羅漢堂には五百羅漢のほかに十六羅漢、釈迦十大弟子の像がズラリ
-
と 鞆の津の商家
- [ 歴史的建造物 ]
-
福山市鞆町鞆606
江戸末期建造の母屋と土蔵からなる商家
母屋の内部は通り庭形式の三間取りで、店の間、中の間、奥の間の三室を配し、商家の建築様式の一つ。入口の格子や
- [ 寺院 | 花 ]
-
府中市目崎町258
別名『さつき寺』と呼ばれる。
5月には、3,000本のさつきが咲き誇る安楽寺。5月のゴールデンウイーク期間に行われるサツキ祭りでは、献花
-
お おかかえ地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
竹原市本町3
気軽に試すことができる「おかかえ地蔵」
竹原まちなみ竹工房の脇の路地を上った所に祀られている地蔵。願い事を胸に祈りながら地蔵を抱え、想像したより軽