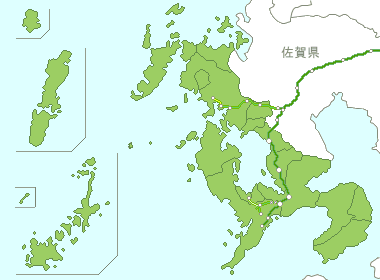神社・寺院・歴史 一覧

-
え 江上教会
- [ 教会 ]
-
五島市奈留町大串1131
大正6(1917)年、御堂造りの名人鉄川与助により建立されたロマネスク様式の教会。コウモリ天井とステンドグ
- [ 歴史 | 公園 ]
-
南島原市有家町尾上5632
町内で発見されたキリシタン墓碑21基が合祀されている。
昭和62年、島原の乱後350年忌の記念事業として設置された西洋墓地風の公園。台付きのカルワリオ十字文、花十
-
き 吉利支丹墓碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
南島原市西有家町須川東向共同墓地内
ローマ字文が刻まれた墓碑として日本最古とされる蒲鉾型の墓碑。
最も美しい形といわれる反円柱蓋石型。碑の背面に薬研彫された大きな花十字紋(碑文は日本最古のローマ字金石文)
-
さ 幸橋オランダ橋
- [ 歴史的建造物 | 橋 ]

-
平戸市岩の上町
三十代平戸藩主の命により元禄15年(1702年)に築造された石造単アーチ橋(重要文化財)。
オランダ商館建造に携わった日本人石工が、地元の石工たちに伝授した架橋技術で建設されたと伝えられるため、オラ
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
五島市奈留町浦1246-2
奈留高校の校庭に、シンガーソングライターのユーミンこと荒井(現姓・松任谷)由実の『瞳を閉じて』が刻まれたユ
-
は はらほげ地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
壱岐市芦辺町諸吉本村触
お地蔵さんが海に浸かっている?
古くから海女の町、八幡の守り神として6体の地蔵が海中に祀られている。名は腹に穴が空いていることに由来する。
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
佐世保市江迎町長坂209
本陣跡は、平戸藩主が参勤交代の折に利用した宿舎。
古くは宿場町として栄えていた佐世保市江迎地区。山下家もと蔵はは元緑年間(1688~1704年)の建造で、内
-
ま 満明寺
- [ 寺院 ]
-
雲仙市小浜町雲仙321
大宝元年(701年)、僧・行基がこの地で温泉山を開山伝わる古い寺。
大宝元(701)年に聖僧行基によって開山したと伝わる真言宗の寺。釈迦堂の中には、5mの純金箔の雲仙大仏が鎮
-
か 海神神社
- [ 神社 ]

-
対馬市峰町木坂247
海の守護神、豊玉姫命(とよたまひめのみこと)を祭る、かつての対馬一の宮。神功皇后の三韓征伐に起源をもつ。伊
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
南島原市深江町戊2133-1
建設省利用活用構想災害メモリアルゾーンの基幹施設としての防災砂防学習施設。
平成3年の雲仙普賢岳の大火砕流によって全焼した小学校を、保存して公開している。国土交通省所管の大野木場砂防
- [ 歴史的建造物 | 歴史 ]
-
長崎市南山手町8-1 グラバー園内
船が三菱造船所のドックに入っている間の乗員たちの宿舎だった建物。
明治29(1896)年に三菱重工長崎造船所が船の修繕所建設に際して建てた洋館。入港した外国船乗組員の休憩・
-
だ 大宝寺(五島市)
- [ 寺院 ]
-
五島市玉之浦町大宝郷631
空海が真言宗を開いたといわれる寺。「西の高野山」と呼ばれ、県の有形文化財に指定されている梵鐘をはじめ、歴史
- [ 歴史 | 公園 ]

-
壱岐市芦辺町深江鶴亀触1092-5
弥生時代の大規模環濠集落で「一支国」の王都に特定された遺跡。
魏志倭人伝に記された「一支国」の王都とされる。多重の濠がめぐる集落や東アジアで最古の船着場が発見された。園
- [ 城 | 歴史 | 博物館・資料館 | 庭園 ]
-
五島市池田町1-4
福江城(石田城)は文久3(1863)年に15年の歳月をかけて福江藩最後の藩主五島盛徳が黒船来航にそなえて建
-
い 壱岐風土記の丘
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
壱岐市勝本町布気触324-1
古墳館も整備され、壱岐の古墳群散策を楽しむ玄関口
掛木古墳をはじめ点在する古墳をめぐりながら散策できる歴史公園。古民家園には壱岐独特の百姓武家建築を移築復元
-
お 男嶽神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
壱岐市芦辺町箱崎諸津触
御祭神は猿田彦命(さるたひこのみこと)。石猿群で知られる。拝殿横の石段に200体を超す石猿が並んでいる。か
-
お 大浦国際墓地
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
長崎市川上町
1861年に開かれた国際墓地。
文久元(1861)年、安政の開国後に設けられた川上町の丘に墓碑が並ぶ。アメリカ人水兵の墓や、丸山花月の門前
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
長崎市伊良林2-9-2
地元の「亀山社中ば活かす会」により運営
会員数100余名の「亀山社中ば活かす会」が管理・運営する資料館。坂本龍馬の等身大パネルや手紙の写しなど関連
-
さ 最教寺
- [ 寺院 ]
-
平戸市岩の上町1206
西の高野山と呼ばれる最教寺。
3万坪におよぶ境内には慶長14(1609)年建立の本堂と、平成元年に完成した真っ赤な三重塔がある。奥の院に
-
な 長崎原爆資料館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
長崎市平野町7-8
核兵器のない世界をめざして、多くの資料を展示。
展示室には900点ほどの原爆資料を展示。ほぼ原寸大に再現した浦上天主堂の再現造型コーナーや、爆風で変形した
-
の 野首天主堂
- [ 教会 | 歴史的建造物 ]
-
北松浦郡小値賀町野崎郷692第1
野崎島にある天主堂で、明治41(1908)年に赤レンガで建造されたもの。「長崎の教会群とキリスト教関連遺産
-
ば 万松院
- [ 寺院 ]
-
対馬市厳原町西里192
初代対馬藩主・宗義智の菩提寺。
日本三大墓地の一つに数えられる対馬島主宗家の墓所がある寺院。宗氏第二十代義成が、父義智の冥福を祈って建立し
-
ひ 日野江城跡
- [ 城 | 歴史 ]
-
南島原市北有馬町戊谷川名
有馬氏の始祖の高来郡を領する経澄が築いたもの。
鎌倉時代前期に初代有馬経澄が築いた城。以後、約400年にわたって有馬氏の居城。十三代目当主有馬晴信はキリシ
-
ひ 平戸城

- [ 城 | 歴史 ]

-
平戸市岩の上町1458
宝永元年(1704年)に日本唯一の山鹿流兵法によって築城された。
現在の天守閣は昭和37年(1962年)に復元され、天守閣内部には3世紀ごろの「環頭の太刀(かんとうのたち)
-
あ 青砂ヶ浦天主堂
- [ 教会 ]
-
南松浦郡新上五島町奈摩郷1241
「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を構成する教会堂のひとつ。
五島列島の中通島北部、奈摩湾を望む高台に建つレンガ造りの教会堂。明治43(1910)年に教会堂建築士として
-
お 大曽教会
- [ 教会 ]
-
南松浦郡新上五島町青方郷2151-2
豊かな緑に囲まれた美しいレンガ造りの教会。
1879年(明治12)に建造され、現在の建物は1916年(大正5)に鉄川与助の設計施工で再建されたもの。ス
-
く 玖島城跡
- [ 城 | 歴史 | 桜 | 花 ]
-
大村市玖島1-45-3
大村藩主の居城であった玖島城跡。
慶長4(1599)年に第十九代大村喜前が築城。工事は長崎惣兵衛が監督。大村喜前の父は日本最初のキリシタン大
-
さ 斎藤茂吉歌碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
雲仙市小浜町北本町
歌碑が夕陽の広場公園の入り口に立つ。
歌人・斎藤茂吉が長崎医専教授時代にここを訪れた際に詠んだ歌の歌碑が「夕日の広場」に建てられている。
-
は 春一番発祥の地
- [ 碑・像・塚・石仏群 | その他 ]
-
壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦403
その昔、このあたりの延縄漁船が2度までも春先の強い風を受けた影響で沈没したことから、島の人が呼びはじめた「
- [ 歴史的建造物 | 歴史街道 | 歴史 ]
-
長崎市東山手町6-25
東山手洋風住宅郡の中の一棟。
長崎市の有形文化財に指定されている7つの洋風住宅「東山手洋風住宅群」の一つ。外国人居留地だった時代の東山手