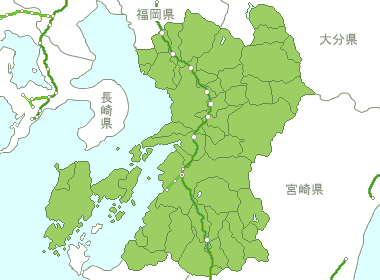神社・寺院・歴史 一覧

-
つ 通潤橋

- [ 歴史的建造物 | 橋 | 珍スポット ]

-
上益城郡山都町下市
「空を渡る水路」通潤橋
1854年(嘉永7)にできた日本最大の水道橋(重要文化財)で、長さは75.6m、高さは20.2m。石橋中央
-
ひ 人吉城跡

- [ 城 | 歴史 | 公園 | 桜 | 紅葉 ]
-
人吉市麓町
人吉の領主相良氏の居城跡で日本百名城の一つ。繊月城とも呼ばれ、球磨川とその支流胸川を利用して天然の外濠とし
-
き 旧細川刑部邸
- [ 歴史的建造物 ]
-
熊本市古京町3-1
細川家三代、忠利の弟にあたる興孝が興じた細川刑部家の武家屋敷(熊本県の重要文化財)で、熊本城三の丸にある。
-
う 宇賀岳古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
宇城市松橋町松山3666-5
岡岳公園内にある古墳時代後期の巨石横穴式装飾古墳。通称「鬼の岩屋」と呼ばれている。
- [ 寺院 | 観音 ]
-
菊池市大平367
黄金色に輝く仏像が列をなす、ぼけ封じ・長生き観音。九州の菊池三十三観音札所の3札番として、興福寺に建立され
-
た 田浦阿蘇神社
- [ 神社 ]
-
葦北郡芦北町田浦1250-1
郷社(ごうしゃ)として肥後十社に数えられている神社。
室町時代の豪族田浦(檜前)氏によって創建されたと伝わる神社。神殿は寛永18(1641)年に焼失してしまい、
-
ふ 藤崎八旛宮
- [ 神社 | 初詣スポット ]
-
熊本市井川淵町3-1
承平5年(935年)、敕願により藤原純友の乱の追討と九州鎮護のために、国府の所在地であった宮崎庄の茶臼山に
-
ほ 宝来宝来神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
阿蘇郡南阿蘇村大字河陰2909-2
宝くじ祈願・開運祈願で知られる。別名、当銭神社と呼ばれている。御神体は当銭岩で金運の神様が勢揃いしている。
-
に 日輪寺
- [ 寺院 ]

-
山鹿市杉
桜とつつじの名所
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]
-
合志市野々島天神免4710-1
縄文時代晩期の遺跡で石器をつくっていた跡といわれ、数多くの打製石器が出土している。
- [ 神社 | 初詣スポット ]
-
熊本市中央区水前寺公園8-1
出水神社
熊本市の水前寺成趣園内にある神社。熊本藩歴代藩主を祀る神社として、明治時代に旧藩士らによって創建された。藩
-
か 加藤神社
- [ 神社 | 初詣スポット ]

-
熊本市中央区本丸2-1
元は慶長16年(1611年)の清正の歿後に加藤清正公を祀った浄地廟。神仏分離により明治元年(1868年)、
-
こ 康平寺
- [ 寺院 ]

-
山鹿市鹿央町霜野
千手観音立像等が奉られている霜野康平寺
平安時代に開基されたといわれる康平寺は、うっそうと茂る木々に囲まれた由緒あるお寺。千手観音立像や二十八部衆
-
つ 塚原古墳群
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
熊本市塚原1924
塚原古墳公園として、前方後円墳、方形周溝墓、円墳他77基の古墳群とともに整備されている。推定500基にもの
- [ 歴史的建造物 ]
-
熊本市水前寺公園22-16
熊本で最初の西洋建築
明治4(1871)年に開校した熊本洋学校のアメリカ人教師ジェーンズの宿舎跡。熊本で最初に建てられた西洋風木
-
み 宮原観音堂
- [ 観音 ]
-
球磨郡あさぎり町岡原北17
桃山時代に建てられた厨子と推定されていて、熊本県の重要文化財に指定されている。造りは建物寄棟茅葺厨子、中に
-
え 永国寺(人吉市)
- [ 寺院 ]
-
人吉市土手町5
応永17(1410)年に、相良前続が七地(人吉市)にあった東照山清明院を当地に移し、実底超真を招いて開基。
-
た 立田自然公園
- [ 歴史 | 公園 | 自然 ]
-
熊本市黒髪4-610
立田山南麓に位置する肥後藩主・細川家の菩提寺泰勝寺跡。園内には初代細川藤孝夫妻と二代細川忠興夫妻の墓が4つ
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
玉名市岩崎117
「河とともに発展した玉名」をテーマに、歴史と文化を紹介する。「日置氏全盛の時代(古代)」「海外交易の時代(
-
ち チブサン古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
山鹿市城西福寺
6世紀初めの古墳時代に築造された前方後円墳。石棺の正面の石板装飾の絵柄が乳房に見えることから、「チブサン」
-
あ 青井阿蘇神社
- [ 神社 ]

-
人吉市上青井町118
楼門・拝殿・幣殿・廊・神殿いずれも国指定重要文化財
「球磨で名所は青井さんの御門」と民謡球磨の六調子に歌われる。大同元(806)年に創建され、慶長15(161
-
へ 幣立神社
- [ 神社 | パワースポット ]

-
上益城郡山都町大野
醍醐天皇の地方巡視の時建立,健磐龍命を主神とする。
大日本史に見える知保(ちほ)の高千穂嶺が当宮の所在地である。筑紫の屋根の伝承のように神殿に落ちる雨は東西の
-
こ 金剛乗寺の石門
- [ 寺院 ]
-
山鹿市山鹿1592
寺の入り口にある石門は、文化元(1804)年に石工・甚吉によって造られたもので、アーチ状で円形の通路と屋根
-
あ 荒茂山勝福寺
- [ 寺院 ]
-
球磨郡あさぎり町荒茂
平重盛の供養のため、養和年間(1181)年ころに創建された伝わる。勝負の神様として評判。毘沙門天立像はクス
-
い 岩崎神社
- [ 神社 ]
-
八代市千丁町太牟田上土374-1
千丁の地は約505年前、上土(あげつち)城主・岩崎主馬(しゅめ)忠久公が領内でい草を植えて以来、日本一の畳
-
う 雲巌禅寺
- [ 寺院 ]
-
熊本市松尾町平山589
南北朝時代、禅僧・東陵永璵により建立されたと伝えられる。通称は岩戸観音。金峰山山麓の岩肌に、
-
さ 崎津天主堂
- [ 教会 ]
-
天草市河浦町崎津539
昭和9(1934)年ハルブ神父により作られた教会。尖塔がそびえるゴシック様式で、聖堂内は畳敷きという和洋の
- [ 観音 ]
-
球磨郡多良木町黒肥地栖山
鎌倉中期のものと推定され、クス一本で造られた高さ2.83mの千手観音像。相良三十三観音の23番札所にあたる
- [ 神社 | 桜 ]
-
菊池市隈府1257
明治3(1870)年に菊池氏居城跡に創建された神社。南北朝時代に南朝側で戦った菊池氏の3代武時公、武重公、
-
の 野津古墳群
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
八代郡氷川町野津~大野
山頂の頂上部に造られた全長約100mの前方後円墳4基(物見櫓古墳・姫の城古墳・中の城古墳・端の城古墳)から