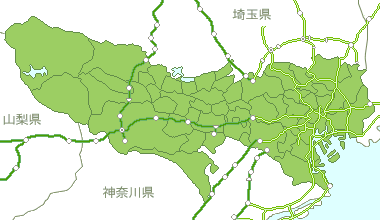神社・寺院・歴史 一覧

-
は 幡ヶ谷不動尊
- [ 寺院 | 不動 ]
-
渋谷区本町2-44-3
荘厳寺(しょうごんじ)は弘法大師が開いた真言宗の寺。一般には幡ヶ谷の不動様、幡ヶ谷不動尊などで知られている
-
は 服部屋敷跡
- [ 歴史 ]

-
八丈町樫立2010
旧幕時代のお船預かり、服部家の屋敷跡。
流人・近藤富蔵の築いた玉石垣に囲まれ、館内には服部家ゆかりの器や道具類を展示。樹齢700年とも言われる敷地
-
み 妙寿寺
- [ 寺院 ]

-
世田谷区北烏山5-15-1
烏山寺町26寺院の内の1つ。
寛永8年(1631)江戸谷中に日受上人が妙感寺と号して開山。心学者中沢道二や政治家川島正次郎の墓所、明治期
-
も 百草八幡宮
- [ 神社 ]

-
日野市百草12-867
八幡神社(百草)百草園に隣接。
康平5年(1062)源頼義が奥州征伐の折、この地をよぎられ再建されたと伝わる。境内は樹齢400年以上ものシ
-
や 矢先稲荷神社
- [ 神社 | 稲荷 | 初詣スポット ]
-
台東区松が谷2-14-1
福禄寿をお祀りしている神社。
寛永19(1642)年3代将軍家光が国家の安泰と市民の安全祈願ならびに武道の練成のために、江戸浅草のこの地
-
や 靖國神社
- [ 神社 | 初詣スポット | 桜 | 紅葉 | パワースポット ]

-
千代田区九段北3-1-1
[ 紅葉時期 11月中旬~12月中旬 ]
日本の軍人、軍属等を主な祭神とする神社
幕末から第二次世界大戦までの間、国を守るために亡くなった246万6532柱(はしら)の神霊を祀る神社。境内
-
あ 浅草神社
- [ 神社 ]

-
台東区浅草2-3-1
浅草寺本堂隣り、浅草寺の境内にある神社。
創建は平安時代後期から鎌倉時代といわれ、浅草寺の縁起となった兄弟の浜成、竹成と土師真中知を祀ったもの。通称
- [ 神社 ]
-
新宿区赤城元町1-10
明治維新までは赤城大明神や赤城明神社と呼ばれた。
鎌倉時代正安2(1300)年、上野国勢多郡宮城村三夜沢の赤城神社の分霊を祀ったのが始まり。岩筒雄命(いわつ
-
い 易行院
- [ 寺院 ]
-
足立区東伊興4-5-5
足立区東伊興にある浄土宗寺院
日照山易行院不退寺と号し、芝増上寺末。歌舞伎では有名な助六とその愛人揚巻。ふたりの仲の良さから「助六と揚巻
-
い 石川啄木歌碑
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
台東区西浅草1-6-1 等光寺内
浅草の夜の寂寥感をうたった歌碑。
歌碑は、啄木生誕七十年にあたる昭和三十年に建てられた。「一握の砂」から次の句が記される。等光寺の境内にあり
-
お 大森貝塚
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 | 庭園 ]
-
品川区大井6-21-6
1877年、日本で初めて発掘された貝塚跡。
アメリカ人の動物学者・エドワード・S・モースが、1877年(明治10年)6月19日に横浜から新橋へ向かう途
-
お 小野照崎神社
- [ 神社 ]
-
台東区下谷2-13-14
江戸時代の富士山信仰が残る神社。
小野篁を主祭神とし、相殿に菅原道真を祀る。852年(仁寿2年)この地の住民が上野照崎の地に小野篁を奉斎した
-
き 喜之床跡
- [ 歴史 ]
-
文京区本郷2-38-9
石川啄木が明治42(1909)年より、妻・子・母を上野駅に迎え、2年2ヶ月過ごした住居の跡。旧家屋は春日通
-
き 絹の道
- [ 歴史街道 ]
-
八王子市鑓水
幕末から明治にかけて、八王子から横浜へ生糸を運んだ道。
大塚山公園付近は、林の中を昔ながらの峠道が通っている。鑓水[やりみず]商人の屋敷跡には絹の道資料館(料金:
-
げ 源覚寺
- [ 寺院 ]
-
文京区小石川2-23-14
徳川秀忠、徳川家光から信仰を得ていた寺院。
寛永元年(1624年)に定誉随波上人(後に増上寺第18世)によって創建され、眼病治癒祈願に多くの人が訪れる
-
こ 弘福寺
- [ 寺院 ]
-
墨田区向島5-3-2
隅田川七福神のうち布袋像を祀る。
1673年(延宝元年)黄檗宗の僧鉄牛道機の開山、稲葉正則の開基により香積山弘福寺を現在地に移して建てられた
-
こ 子安神社
- [ 神社 ]
-
八王子市明神町4-10-3
八王子の最古の神社安産・子育・厄除祈願で有名
奈良時代に皇后の安産のために創建されたといわれる神社で、木花開耶姫命、天照大御神、素盞鳴尊、大山咋命、奇稲
-
こ 近藤勇生家跡
- [ 歴史 ]
-
調布市野水1-6-8
菩提寺である龍源寺の西に、新選組局長・近藤勇の生家跡があります。
7000平方メートルの敷地に堂々と建つ屋敷だったと伝えられる。昭和18年の戦時中に調布飛行場に隣接の為取り
-
し 芝東照宮
- [ 神社 ]
-
港区芝公園4-8-10
1641(寛永18)年創建。祭神は徳川家康。神体は徳川家康寿像。旧社格は郷社。日光東照宮、久能山東照宮、上
-
し 芝大神宮
- [ 神社 ]

-
港区芝大門1-12-7
東京十社の1社で、旧社格は府社。
伊勢神宮の内外両宮の祭神を祀ることから、関東における伊勢信仰の中心的な役割を担い、「関東のお伊勢様」として
-
じ 深沙堂
- [ 寺院 ]

-
調布市深大寺元町5-12-8
昭和四十三年(1968)に再建されたもので、入母屋(いりもや)造り銅板葺き、妻入り。一般参拝は不可で、深大
- [ 神社 ]

-
中央区佃1-1-14
摂津国西成郡田蓑島(現大阪市西淀川区佃)の漁民が、本能寺の変で徳川家康を助けた功により江戸に呼び寄せられた
-
せ 専光寺
- [ 寺院 ]
-
世田谷区北烏山4-28-1
烏山寺町にある26の寺院のうちの1つ。
境内には江戸時代後期に美人画の作者として活躍した喜多川歌麿の墓があり、毎年9月20日の命日前後に供養が行わ
-
ね 根津神社
- [ 神社 | ツツジ | パワースポット ]

-
文京区根津1-28-9
つつじの名所として有名。
日本武尊が1900年近く前に創祀したと伝える古社で、東京十社の一つに数えられている。徳川5代将軍綱吉により
-
ほ 宝泉寺(日野市)
- [ 寺院 ]
-
日野市日野本町3-6-9
鳥羽伏見の戦いで戦死した井上源三郎の墓・顕彰碑がある寺。
墓前には子孫が管理している「墓前ノート」があり、全国から訪れたファンのメッセージがつづられています。臨済宗
-
み 御田八幡神社
- [ 神社 ]

-
港区三田3-7-16
和銅2年(709年)8月、東国鎮護の神として牟佐志国牧岡の地に祀られたのに始まる神社。誉田別尊命を主祭神と
-
も 物忌奈命神社
- [ 神社 ]

-
神津島村41
島の開祖・物忌奈命を祀る社。
島民の守護神。参道にはタブノキ、ツバキ、マキなどの樹木が生い茂る。7月31日~8月2日の例大祭では、かつお
-
あ 阿波命神社
- [ 神社 ]

-
神津島村長浜
村落から徒歩約一時間の長浜海岸の山側奥に鎮座
伊豆諸島を創造したアワノミコトを祀り、別名・長浜神社ともいわれている。境内の神域には清流が流れ、厳かな雰囲
-
う 優婆夷宝明神社
- [ 神社 ]

-
八丈町大賀郷7373-8
伊豆七島を創った事代主命の姫、八十八重姫とその子古宝丸を祀る八丈島の総鎮守。社殿には珍しい形式で、キリシタ
-
お 大里神社
- [ 神社 ]
-
青ヶ島村休戸郷
境内には50もの祠がある。
青ヶ島の総鎮守。二重式火山の外輪山の頂上にあり、玉石の急な石段を300段のぼる。「でいらほん祭」「えんだん