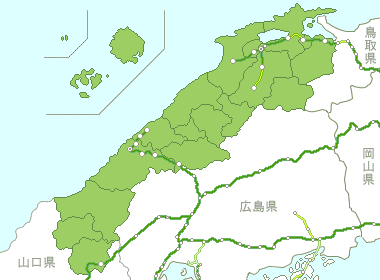観光スポット 一覧

-
く 国賀海岸

- [ 自然 | 自然地形 | 海 | 遊歩道 ]
-
隠岐郡西ノ島町国賀浜
隠岐諸島の西ノ島、北西部に位置する国の名勝に指定された自然景勝地。日本海の風浪に削り取られた大断崖や奇岩怪
-
こ 古浦海水浴場
- [ 海水浴場 ]
-
松江市鹿島町古浦
-
こ 国府海水浴場
- [ 海水浴場 ]
-
浜田市下府町
-
ご 五箇創生館
- [ 博物館・資料館 ]
-
隠岐郡隠岐の島町郡615-1
隠岐の伝統文化を紹介する施設。特殊技術で作られた花のレプリカや牛の剥製などを展示。隠岐伝統行事の牛突きと古
-
さ 西念寺(大田市)
- [ 寺院 ]
-
大田市温泉津町温泉津イ787
毛利元就にゆかりの古刹。
毛利元就が九州の立花城を攻めた際に、手柄のあった然休上人を開基とした浄土宗の寺院。世界の銀産出の三分の一と
-
じ 浄土ヶ浦
- [ 海 | 遊歩道 ]
-
隠岐郡隠岐の島町浄土ヶ浦
大小多数の島々や岩礁が散在し、まるで浄土のように美しい海岸。風光明媚な景勝地で知られ、また隠岐布施海岸の名
-
ぞ 象ヶ鼻
- [ 自然 | 自然地形 | 海 ]
-
隠岐郡隠岐の島町西村
巨象が鼻で海水を吸い上げているように見える「象ヶ鼻」。白い岩肌と松の緑、青い海が美しい白鳥海岸は、オオミズ
-
た 高津川、横道川
- [ 自然 | ホタル ]
-
鹿足郡津和野町左鐙
杣の里へ向かう川沿いは、山が迫り辺りは真っ暗なため、ほたるがいっせいに点滅する様は、まさに星空の世界のよう
-
た 玉作湯神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
松江市玉湯町玉造508
『延喜式』・『出雲国風土記』にも登場する古社。玉造温泉を発見した少彦名命(温泉の神)、天照大神に八尺勾玉を
-
た 太皷谷稲成神社
- [ 神社 | 初詣スポット ]

-
鹿足郡津和野町後田409
通称「津和野おいなりさん」。全国で唯一「いなり」を「稲成」と表記する。
京都の伏見稲荷の神霊を移した神社。稲荷神社のなかでも「稲成」と表記するのはここだけ。大願成就の祈りが込めら
-
な 那久岬海岸
- [ 自然 | 海 | 遊歩道 ]
-
隠岐郡隠岐の島町那久
神功皇后が立ち寄ったという伝説の残る那久岬。高台に展望台があり、天候の良い日には島前を望むことができる。突
- [ 神社 | パワースポット ]
-
雲南市大東町須賀260
和歌発祥の地八雲山山麓に鎮座。須佐之男命と妻の稲田姫の宮作りの地で日本最初の宮であり、大社造りの社殿が歴史
-
ひ 人丸神社
- [ 神社 ]
-
江津市島の星町
高角山の麓にある、江津市ゆかりの万葉歌人、柿本人麻呂を祀る神社。妻への想いを詠んだ「石見のや高角山の木の際
-
ひ 比婆山久米神社
- [ 神社 ]
-
安来市伯太町横屋844-1
標高約280mの山上のある神社、熊野神社(比婆山久米神社)。『古事記』によると伊弉冉尊が祀られた場所とされ
-
ほ 帆掛島
- [ 自然 | 海 | 釣り ]
-
隠岐郡隠岐の島町西村
隠岐諸島に属する日本海の無人島で磯釣りのメッカとして知られる。
-
ほ 堀庭園
- [ 紅葉 | 庭園 ]
-
鹿足郡津和野町邑輝795
裏山を借景とした池泉廻遊式庭園。
旧家・堀家の池泉廻遊庭園。国の名勝に指定されている。堀家の裏山を借景とし、数寄屋造りの客殿「楽山荘」があり
-
み 美保関灯台
- [ 自然 | 灯台 | 日の出 ]

-
松江市美保関町美保関
「世界灯台100選」および「日本の灯台50選」に選ばれている日本を代表する灯台の一つ。
明治31(1898)年に完成した島根半島の先端の地蔵崎に立つ石造りの灯台で、世界歴史的灯台百選に選ばれてい
-
や 弥栄神社
- [ 神社 ]
-
鹿足郡津和野町稲成丁
津和野大橋のたもとに大鳥居がある弥栄神社。正長元年(1428年)三本松城主吉見氏が祇園社の分霊を太鼓谷山に
-
り 龍頭八重滝

- [ 自然 | 川・滝・渓谷 | 紅葉 | 遊歩道 ]
-
雲南市掛合町入間
[ 紅葉時期 10月下旬~11月上旬 ]
龍頭八重滝は松笠地区にある龍頭ヶ滝と、入間地区にある八重滝の総称。
三刀屋川の上流には大小8つの滝が続き美しい渓谷を作っている。上流部の雄滝、下流部の雌滝からなる。流域にはオ
-
ろ ローソク岩観音岩
- [ 観音 | 自然地形 ]
-
隠岐郡西ノ島町浦郷
奇岩怪礁の中で細長くそびえたつ岩。日が沈むころには、ローソクに火を灯したように見え、百済観音の姿にも見える
- [ 道の駅 ]
-
出雲市大社町修理免735-5
- [ 道の駅 ]
-
雲南市木次町山方1134-9
- [ 道の駅 ]
-
鹿足郡津和野町池村1997
-
あ 赤ハゲ山
- [ 山・登山 ]
-
隠岐郡知夫村赤ハゲ山
標高325mの知夫里島の最高峰で輪転式牧畑の名残を残す。山頂には展望台があり、望遠鏡をのぞくと、眼前に広が
- [ 浸かる | シネマ・劇場・ホール ]
-
江津市有福温泉町711
『大蛇[おろち]』など、石見神楽の中から3演目を選び、約1時間に簡略化して上演。
しっとりした情緒が漂う温泉街の小さな演芸場で、勇壮な石見神楽が毎週土曜に上演されている。地元の有福温泉神楽
-
あ 赤尾展望所
- [ 展望台 ]

-
隠岐郡西ノ島町浦郷
赤尾スカイラインの終点にある赤尾展望所。摩天崖・通天橋・天上界など国賀海岸が見渡せる。
- [ 公園 | 桜 ]

-
出雲市平田町
桜の名所として知られ、春には花見を楽しむ観光客で賑わう。
"各種アスレチックなども充実しており市民の憩いの場となっている。春には愛宕山公園西口から続く坂道
-
う 鵜丸城址
- [ 城 | 歴史 ]
-
大田市温泉津町温泉津
鵜丸城は中世の港湾として繁栄した沖泊の南側の丘陵突端に位置する標高59m(比高55m)の海城。
毛利氏によって元亀2年(1571に毛利水軍の拠点として約1か月で築城されたことが「児玉伝右衛門家文書」(萩
-
え えんや温泉
- [ 温泉地 ]
-
出雲市塩冶有原町
希少な高張性の温泉は、さっぱりとした肌ざわりで体がより温まる
出雲市の街中に湧く。温泉のなかでも希少な高張性で、温泉成分が皮膚から体内に吸収されやすいという特徴がよろこ
-
お 乙女峠マリア聖堂
- [ 教会 ]
-
鹿足郡津和野町後田 乙女峠
明治維新後、キリシタン禁令による長崎浦上の36人の殉教者と聖母マリアに捧げる記念堂。殉教者の誉れを記念し1