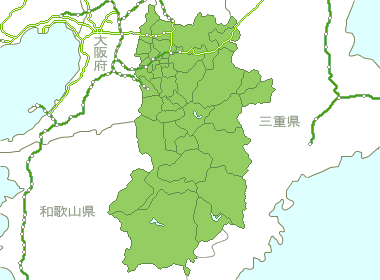神社・寺院・歴史 一覧

-
か 海龍王寺
- [ 寺院 ]
-
奈良市法華寺北町897
天平3年(731年)、光明皇后の発願で建立されたと伝わる。本尊は十一面観音。光明皇后の皇后宮(藤原不比等の
-
こ 興福院
- [ 寺院 ]
-
奈良市法蓮町881
浄土宗知恩院派の尼寺。
開基(創立者)は和気清麻呂ともいい、藤原百川ともいう。もとは僧院だが、徳川家綱の時代に尼寺として再興され現
-
よ 吉野歴史資料館
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-
吉野郡吉野町宮滝348
展示室では、宮滝遺跡から出土した縄文から奈良時代までの遺物や、『万葉集』などにしばしば登場する吉野宮の復元
-
き 喜光寺
- [ 寺院 | 花 ]

-
奈良市菅原町508
奈良時代の高僧・行基が没した地とされている。
行基が721(養老5)年に創建。行基建立の四十九院の一つであるとされている。大仏殿の十分の一の雛型として作
-
し 島の山古墳
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
磯城郡川西町唐院
全長190mの周囲に周濠がめぐる前方後円墳であり、奈良県下の前方後円墳300余基中、第20番目の規模。水を
-
た 當麻寺
- [ 寺院 | 花 ]

-
葛城市當麻1263
白鳳ロマンの里ボタンの寺として有名。
用明天皇第三皇子・麻呂子親王の建立と伝わり、白鳳伽藍を有する古寺。極楽浄土を表した中将姫の當麻曼茶羅で知ら
-
と 東大寺 戒壇堂
- [ 寺院 ]

-
奈良市雑司町
出家者が受戒(正規の僧となるための戒律を授けられる)するための施設として、天平勝宝7歳(755年)に鑑真和
-
あ 安楽寺廃寺跡
- [ 寺院 | 歴史 ]
-
宇陀市菟田野駒帰
昭和45-46年遺構が発見され、現在は史跡公園。
多武峰の談山神社に伝わる「宇陀旧事・写本」の記述からその存在が知られ発掘された。創建時の瓦窯跡が発見され、
-
い 今西家書院
- [ 歴史的建造物 | 庭園 ]

-
奈良市福智院町24-3
室町時代の典型的な書院造りを伝える国の重要文化財。
銀閣寺の東求堂と同じく室町中期の書院造りの最も古い遺構を残しているといわれている。庭を望む書院の落ち着いた
- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 | 遊歩道 ]
-
奈良市都祁南之庄町
西古墳(円形、径40m)と東古墳(前方後円墳、全長110m)の墳丘を発掘調査成果に基づき復元され、公園とし
-
せ 千手院
- [ 寺院 | パワースポット ]
-
生駒郡平群町信貴山2280-1
信貴山真言宗の大本山。
朝護孫子寺の最古の塔頭で、同時に最古の建造物(書院)を有する。本尊は毘沙門天。境内には十一面観音を本尊とす
-
た 龍田神社
- [ 神社 | 紅葉 ]
-
生駒郡斑鳩町龍田1-5-3
崇神天皇の時代に創立され、法隆寺の鎮守とされていた。
伝承によれば、聖徳太子が法隆寺の建設地を探し求めていたときに、白髪の老人に化身した龍田大明神に逢い、「斑鳩
-
ち 長弓寺
- [ 寺院 ]
-
生駒市上町4443
国宝の本堂は鎌倉時代の密教仏堂の代表作として知られる。
728(神亀5)年に行基と建立したと伝わる。境内には庫裏と塔頭四坊が立っている。近くの真弓団地東端に、真弓
-
に 丹生川上神社上社
- [ 神社 ]
-
吉野郡川上村迫869-1
675(白雉26)年、天武天皇によって創建されたと伝えられる古社。
社名は下市町の丹生川上神社下社に対するもの。雨神を祭神として、雨乞いには黒馬、雨止めには白馬を奉り、境内に
-
ひ 一針薬師笠石仏
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
生駒郡三郷町勢野東6-7-27
鎌倉時代に快慶が彫ったと伝わる。
俗に「一針薬師」と呼ばれ、針で刻んだような線刻の薬師如来像をあらわしている。薬師如来像には日光・月光両菩薩
-
れ 歴史の道
- [ 道・通り・街 | 歴史 ]
-
奈良市市内
奈良市街をほぼ一周するように整備されている全長27kmの道。般若寺、秋篠寺、薬師寺、白毫寺を結んだライン。
-
お 多神社
- [ 神社 ]
-
磯城郡田原本町多570
古代の豪族多氏ゆかりの神社。
4座(神八井耳命・神泥川耳命・神倭磐余彦尊・姫御神)の神を主祭神とする。「古事記」を編纂した太安万侶も多一
-
く 栗山家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
五條市五條1-2-8
民家として日本最古の建物。
江戸初期の慶長12年(1607年)の建築で、正面9間・側面6間の入母屋造り。栗山家はそのなかで最も古く、現
-
だ 大願寺(宇陀市)
- [ 寺院 ]
-
宇陀市拾生736
聖徳太子が蘇我馬子に命じて建立したとも伝わる古寺。
創建は推古時代と伝えられる古刹で真言宗御室派、本尊は十一面観音菩薩像(焼けずの観音)。別名「七福寺」。十薬
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
吉野郡十津川村小原225-1
十津川の水害の歴史や村人の暮らしぶりを、パネルを使って紹介。
皇室と深くかかわった村の歴史も知ることができる。近くに伝習館「十津川郷」がある。
-
よ 吉野山の町並み
- [ 歴史 | 桜 ]
-
吉野郡吉野町吉野山
吉野山には古来桜が多く、シロヤマザクラを中心に約200種3万本の桜が密集していて、山中には、金峯山寺などの
-
せ 石光寺
- [ 寺院 | 花 ]

-
葛城市染野387
中将姫ゆかりのボタンの寺。
草創は約1300年前、天智天皇(668~671在位)の勅願で建てられ、役小角(えんのおづぬ)の開山と伝えら
-
む 室生寺 金堂
- [ 寺院 ]
-
宇陀市室生区室生78 室生寺
仁王門をくぐり石段(鎧坂)を登った正面にあるのが、国宝の金堂。
平安初期の建築物で、堂内須弥壇上には向かって左から十一面観音立像(国宝)、文殊菩薩立像(重文)、本尊釈迦如
-
む 室生寺 仁王門
- [ 寺院 ]
-
宇陀市室生78
室生川にかかった朱塗りの太鼓橋を渡り、室生寺へと進むと巨大な仁王門(近代の再建)が立つ。朱塗りの柱と白壁が
-
や 夜支布山口神社
- [ 神社 ]
-
奈良市大柳生町3693
ひっそりと拝殿と本殿が立つ。摂社の立磐神社は春日大社の大四神殿を移築したもので、重要文化財に指定されている
-
が 元興寺

- [ 寺院 ]

-
奈良市中院町11
元興寺は古都奈良の文化財として、ユネスコの世界遺産に登録されたお寺。
南都七大寺の1つに数えられる寺院。蘇我馬子が飛鳥に建立した、日本最古の本格的仏教寺院である法興寺がその前身
-
た 談山神社
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 | パワースポット ]
-
桜井市多武峰319
[ 紅葉時期 11月中旬~12月上旬 ]
木造では世界唯一の十三重塔をはじめとする重要文化財「社殿群」
鎌倉時代に成立した寺伝によると、藤原氏の祖である藤原鎌足の死後の天武天皇7年(678年)、長男で僧の定恵が
-
い 入鹿神社
- [ 神社 ]
-
橿原市小綱町
素戔鳴尊と蘇我入鹿を祭神とし、合祀している。境内には神宮寺として明治時代まで仏起山普賢寺があり大日如来が祀
- [ 寺院 ]
-
北葛城郡広陵町的場80
聖徳太子によって開創されたと伝えられる。
本堂には本尊薬師如来座像のほか、県指定文化財として両界板絵曼荼羅(1422~24年)、長谷寺式十一面観音(
-
に 如意輪寺
- [ 寺院 ]
-
吉野郡吉野町吉野山1024
延喜年間(901年-922年)に日蔵上人により開かれたと伝わる。
南北朝時代、後醍醐天皇の勅願寺となった。裏山の松林には無念の思いで崩御した天皇の御陵が、京都に向かって築か