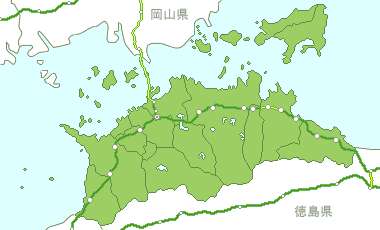神社・寺院・歴史 一覧

-
し 志度寺
- [ 寺院 | 庭園 ]
-
さぬき市志度1102
創建は626年(推古天皇33年)と伝わる。戦国時代に戦乱により寺院は荒廃。藤原氏末裔の生駒親正による支援な
-
あ 有岡古墳群
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
善通寺市善通寺町、生野町
大麻山山麓に点在する6基の古墳(野田院古墳・王墓山古墳・宮が尾古墳・磨臼山古墳・丸山古墳・鶴が峰4号墳)は
-
こ 木烏神社・千歳座
- [ 神社 ]
-
丸亀市本島町泊
讃岐の国造、武殻王が近海を荒らす魚を退治する際に案内役を務めたとされる伝説の烏(カラス)を祀る神社。境内に
-
ほ 細川家住宅
- [ 歴史的建造物 ]
-
さぬき市多和額東46
讃岐で生産された塩を志度から阿波に運んでいた街道沿いにある江戸中期の代表的な農家で、国の重要文化財。軒先ま
-
ご 郷照寺
- [ 寺院 ]

-
綾歌郡宇多津町1435
四国八十八箇所霊場の第七十八番札所。
行基が神亀2年(725年)に阿弥陀如来を本尊として開基、当初は道場寺と呼ばれていた。弘仁6年(815年)に
-
じ 鷲峰寺
- [ 寺院 ]
-
高松市国分寺町柏原632-3
四国霊場第82番札所根香寺の奥の院
奈良時代の天平勝宝6年(754年)唐僧・鑑真により建立したという。本尊は千手千眼観世音菩薩。四国八十八箇所
- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]
-
高松市朝日町3-6-38
2019年3月24日に閉館「平家物語」の名場面を、等身大のろう人形でリアルに再現した歴史館。1階には、四国
-
み 三谷寺
- [ 寺院 ]
-
丸亀市飯山町東坂元
讃岐33観音26番札所霊場地。
天平2(730)年に僧行基が聖武天皇の勅願所として創建した、讃岐三十三観音第26番札所。境内には弘法大師、
-
か 冠纓神社
- [ 神社 ]
-
高松市香南町由佐1413
貞観3(861)年、円珍の創建とされる。別名は「かむろ八幡宮」で、香南町の氏神として親しまれ、縁結び神社と
-
さ 最明寺(高松市)
- [ 寺院 | 花 ]
-
高松市塩江町安原下第1号274
最明寺は四国を代表する萩の名所
大宝元(701)年、行基が伽藍を建立。如意輪寺からのちに最明寺に改称したとされる。境内には現在、ミヤギノハ
-
ぶ 武家屋敷
- [ 歴史 | その他 ]
-
仲多度郡多度津町家中
長屋や武家屋敷などの城下町の名残りを見せる。
桜川から北に入った一角。江戸時代に、藩主京極高賢が設けた陣屋(武家屋敷)町で、城下町の繁栄を今に伝える。御
-
ど 道隆寺
- [ 寺院 ]
-
仲多度郡多度津町北鴨1-3-30
和銅5年、当地の領主である和気道隆が乳母を誤って射殺してしまったため、これを悲しんで桑の大木を切り、薬師如
-
や 八栗寺
- [ 寺院 | 初詣スポット ]
-
高松市牟礼町牟礼3416
829(天長6)年、弘法大師の開基。本尊は聖観世音菩薩。五剣山の中腹に立つ。寺名は空海が植えた8つの焼き栗
-
じ 神恵院
- [ 寺院 ]
-
観音寺市八幡町1-2-7 観音寺内
日証上人が開いた琴弾八幡宮と別当神恵院が由来。行基が養老6年(722年)に訪れた後、大同2年に空海(弘法大
-
い 厳魂神社(奥社)
- [ 神社 ]
-
仲多度郡琴平町892-1 金刀比羅宮内
金刀比羅宮御本宮から、さらに583段の石段を登った所にある。奥社の西側の垂直に切り立った岩壁の上には、荒々
-
か 神谷神社
- [ 神社 ]
-
坂出市神谷町621
弘仁3年(812年)、空海の叔父にあたる阿刀大足(あとのおおたり)が社殿を造営し、相殿に春日四神を勧進した
-
こ 甲山寺
- [ 寺院 ]
-
善通寺市弘田町1765-1
弘法大師(空海)が満濃池を改修し、弘仁12年(821年)、報奨金で堂宇を建て、自作の薬師如来像を安置したと
-
し 出釈迦寺
- [ 寺院 ]
-
善通寺市吉原町1091
7歳の時に弘法大師(空海)が仏道に入ることを決めた場所。大師はのちに我拝師山の麓で釈迦如来像を刻み、この寺
-
じ 地蔵院萩原寺の萩
- [ 寺院 | 碑・像・塚・石仏群 | 花 ]
-
観音寺市大野原町萩原2742
秋になると境内に約2000株の萩が花をつける。
萩原寺は萩の名所で、9月から10月には約2500株の薄紫や白の小花を枝いっぱいに散りばめた萩を見ることがで
- [ 寺院 ]
-
三豊市山本町辻4209
天平14(742)年、東大寺の末寺として建立され、弘仁13(822)年、嵯峨天皇の勅願により空海(弘法大師
-
い 一宮寺
- [ 寺院 ]
-
高松市一宮町607
大宝年間(701年-704年)に大宝院として義淵が創建し、後に行基が一宮寺と改めたと伝わる。その後大同年間
-
は 萩原寺
- [ 寺院 | 花 ]
-
観音寺市大野原町萩原2742
大同2(807)年空海(弘法大師)が建立したという。巨鼇山地蔵院萩原寺と号する。平安期には仏教隆盛の拠点と
-
も 本山寺
- [ 寺院 ]
-
三豊市豊中町本山甲1445
高野山真言宗の寺院。
寺伝によれば、大同2年(807年)、平城天皇の勅願寺として、空海(弘法大師)が自ら刻んだ馬頭観世音菩薩像を
-
あ 粟井神社
- [ 神社 | あじさい ]
-
観音寺市粟井町1716
岩鍋池の畔にあるアジサイで有名な神社。
かつては刈田大明神と称し、今はアジサイ神社の名で親しまれる。境内には約3,000株のアジサイが植えられてお
-
た 田村神社
- [ 神社 | パワースポット ]
-
高松市一宮町286
讃岐一宮で別称として、田村大社・一宮神社・定水大明神・一宮大明神・田村大明神ともいう。奈良時代からの由緒深
- [ 神社 ]
-
高松市男木町134
安産の神様豊玉姫を祭る神社
男木島、女木島、直島の氏神だった男木島の豊玉姫神社は安産の神として信仰を集めていた。境内からの眺めも素晴ら
-
よ 與田寺
- [ 寺院 ]
-
東かがわ市中筋466
さぬき七福神の一つ(寿老人)、四国八十八箇所総奥の院。
奈良時代の天平11年(739年)に行基を開山として醫王山薬王寺薬師院の号で法相宗の寺院として創建したとされ
- [ 神社 | 梅 ]

-
綾歌郡綾川町滝宮1314
学問の神様・菅原道真を祭る神社。
948(天暦2)年に創建。菅原道真が国司として在任した官舎跡に建てられた。道真真筆の自画像、書状などを所蔵
-
な 長尾寺
- [ 寺院 ]

-
さぬき市長尾西653
聖徳太子の開創といわれ、聖武天皇(724)、天平11年(739)に行基菩薩がこの地を訪れ、霊感を得られ柳の
-
ほ 法然寺
- [ 寺院 ]
-
高松市仏生山町甲3215
高松藩主松平家の菩提寺。
江戸時代からの歴史ある高松藩主松平家の菩提寺。法然上人25霊場第2番札所。有名な讃岐の寝釈迦(涅槃像)があ