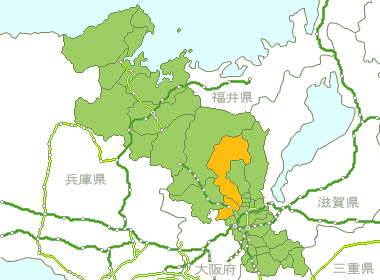神社・寺院・歴史 一覧
-
嵐山・嵯峨・高山寺

-
だ 大心院
- [ 寺院 ]
-
京都市右京区花園妙心寺町57
三様(阿吽庭・牡丹の庭・清竹の庭)の庭園が楽しめる。
室町期1479年(文明11)、細川政元によって創建された臨済宗の寺。天正年間(1573~1592年)に細川
-
ま 松尾大社
- [ 神社 | 庭園 ]
-
京都市西京区嵐山宮町3
701(大宝元)年に秦氏が創建した京都最古の社。
式内社(名神大)、二十二社の一社で、旧社格は官幣大社。旧称松尾神社。境内奥の「亀井の水」は延命長寿の名水で
-
さ 西院春日神社
- [ 神社 | 初詣スポット ]

-
京都市右京区西院春日町61
春日神(建御賀豆智命・伊波比主命・天児屋根命・比売神)を祀る。
平安時代の創建以来、病気平癒のご利益が高いことで知られる。春日祭(10月第2日曜に行われる祭)では、東組、
-
じ 地蔵院(竹の寺)
- [ 寺院 ]
-
京都市西京区山田北ノ町23
衣笠山と号する臨済禅宗の寺。
南北朝時代に管領の細川頼之が夢窓疎石の高弟宗鏡禅師を開山として建立した寺。現在の本堂は(地蔵堂)は、昭和1
-
た 滝口寺
- [ 寺院 ]
-
京都市右京区嵯峨亀山町10-4
鎌倉時代創建の三宝寺の跡地に、法然の弟子念仏房良鎮が開創した浄土宗の寺。堂内に『平家物語』で知られる滝口入
-
ね 念仏寺
- [ 寺院 ]
-
京都市右京区山ノ内宮前町12
浄土宗西山禅林寺派の寺。
本堂には妙徳婦人母子像を奉安し、水子供養の寺として知られている。また、母子の安泰、参詣の人々の福寿繁栄と無
-
こ 金蔵寺
- [ 寺院 | 紅葉 ]
-
京都市西京区大原野石作町1639
天正天皇の勅命により隆豊(りゅうほう)禅師により創建。
平安末期の説話集『今昔物語』に登場する歴史ある寺。小塩山の中腹、標高約350mに位置し、境内からは京都市街
-
え 厭離庵
- [ 寺院 | 紅葉 ]
-
京都市右京区嵯峨二尊院門前善光寺山町2
「小倉百人一首」の藤原定家(ふじはらていか)ゆかりの非公開寺。
現在の本堂、茶室の時雨亭は明治になって、貴族院議員であった白木屋社長(大村彦太郎)によって建立されたもの。
-
ほ 法輪寺(京都市)
- [ 寺院 ]

-
京都市西京区嵐山虚空蔵山町
和銅6年(713年)奈良時代に行基が開いたとされる古刹。
本尊の虚空蔵菩薩が、「嵯峨の虚空蔵さん(さがのこくうぞうさん)」として親しまれている。嵐山の中腹にあり、境
-
ぎ 祇王寺
- [ 寺院 ]

-
京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町32
真言宗大覚寺派の仏教寺院の尼寺。
元々は浄土宗の僧・良鎮が創建した往生院の跡を引き継いで今日に至る。平清盛の寵愛を受けた白拍子の祇王が、清盛
-
じ 常照皇寺
- [ 寺院 | 庭園 | 桜 ]
-
京都市右京区京北井戸町丸山14-6
南北朝時代、北朝初代の天皇となった光厳上皇が出家した後、1362(貞治元)年に草庵を営んだのが寺の起源。本
-
さ 三宝寺(京都市)
- [ 寺院 | 桜 ]

-
京都市右京区鳴滝松本町32
寛永5(1628)年後水尾天皇の勅命により開山したお寺。
境内には御所より移植したと伝える、名桜「御車返しの桜」や樹齢700年の楊梅(やまもも)などがある。中本山「
-
さ 三鈷寺
- [ 寺院 ]
-
京都市西京区大原野石作町1323
西山宗の寺院で本尊は如法仏眼曼荼羅。
開山は源算上人で、1074年(承保1)建立の往生院が前身で、四祖證空(西山国師)が念仏道場として発展させた
-
り 龍安寺のつくばい
- [ 寺院 ]
-
京都市右京区龍安寺御陵下町13 龍安寺内
龍安寺の石庭が名高い方丈の北東にある銭形のつくばい。
四文字が刻まれていて、中心の口を共用して読めば「吾唯足知(われただたるをしる)」と禅の格言を表している。
-
あ 化野念仏寺
- [ 寺院 | 珍スポット ]

-
京都市右京区嵯峨鳥居本化野町17
洛北の蓮台野と並ぶ平安時代以来の墓地で、風葬の地として知られる。
約1200年前、風葬の地だった化野に葬られた無縁仏を弘法大師空海が五智山如来寺を建てて供養したのが始まり。
-
た 退蔵院
- [ 寺院 ]

-
京都市右京区花園妙心寺町35
初期水墨画の代表作である国宝・瓢鮎図を所蔵することで有名。
1404年(応永11年)に越前の豪族・波多野重通(はたのしげみち)が妙心寺第三世・無因宗因(むいんそういん
-
ほ 法金剛院
- [ 寺院 | 花 | 庭園 ]
-
京都市右京区花園扇野町49
平安時代の浄土式庭園を残す寺として知られる。
平安時代初期の右大臣の清原夏野の別荘があった旧跡を、1130(大治5)年に鳥羽天皇の中宮が再興した寺。昭和
-
だ 檀林寺
- [ 寺院 ]
-
京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町2-10
平安時代815年(弘仁6)に嵯峨天皇の皇后橘嘉智子が創立した寺。
唐の僧義空和尚を師として日本で最初に禅が教えられたところといわれる。宝物館には彫刻、絵画を始め多く日本と中
-
し 正法寺(京都市)
- [ 寺院 | 庭園 | 桜 | 紅葉 ]

-
京都市西京区大原野南春日町1102
[ 紅葉時期 11月上旬~11月下旬 ]
鑑真和尚の高弟、智威大徳が隠棲したことに始まる真言宗の寺院。
弘仁年間の時、弘法大師巡錫され四十二歳の厄除けのため、聖観音を彫刻されました。本堂、宝生殿の庭園には高知、
-
じ 十輪寺
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 ]
-
京都市西京区大原野小塩町481
在原業平と清和天皇の妃、藤原高子の恋物語の舞台。
850年(嘉祥3)文徳天皇が染殿皇后の安産祈願のため伝教大師作の延命地蔵を安置したのが起こりと伝わる。本尊
-
ほ 宝厳院
- [ 寺院 | 庭園 | 紅葉 ]

-
京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町36
臨済宗天龍寺派の寺院で天龍寺の塔頭。
寛正2年(1461年)、細川頼之が聖仲永光を開山に招聘して創建。応仁の乱(1467年-1477年)に巻き込
-
た 退蔵院の水琴窟
- [ 寺院 ]
-
京都市右京区花園妙心寺町35 退蔵院内
癒しを与える音、水琴窟。
妙心寺の塔頭、退蔵院「余香苑」のかたわらにある水琴窟は、耳を澄ますと小さく響く音がする。「つくばい」の下深
-
い 印空寺
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 ]
-
京都市右京区山越西町8
長岡京の光明寺が総本山で西山浄土宗の寺。
1688年、美濃・立政寺より印空が入り、仁和寺門跡・寛隆法親王より寺領寄進を受けて建立。白梅、枝垂れ桜、の
-
と 東林院
- [ 寺院 | 花 ]
-
京都市右京区花園妙心寺町59
妙心寺の塔頭のひとつ。
沙羅双樹の寺として知られる。沙羅双樹が花開く6月15日から30日まで「沙羅の花を愛でる会」として境内が公開
-
あ 油掛地蔵
- [ 碑・像・塚・石仏群 ]
-
京都市右京区嵯峨天竜寺油掛町
右京区嵯峨の小さな祠に鎮座する石造阿弥陀坐像。
鎌倉時代に創られた阿弥陀如来(石仏)。油をかけて祈願すると諸願成就するといわれ、体中が油にまみれている。京
-
せ 清凉寺 霊宝館
- [ 寺院 ]
-
京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町46 清凉寺
清凉寺の寺宝を所蔵・展示。
釈迦如来像(国宝)の胎内から発見された五臓六腑(絹製の内臓の模型)を所蔵していて、複製が春と秋に一般公開さ
-
ふ 福徳寺
- [ 寺院 ]
-
京都市右京区京北下中町寺ノ下15
和銅4年(711)、行基の開創と伝えられる古刹。
薬師堂に本尊薬師如来坐像、持国天立像、増長天立像と、3体の重要文化財を安置する。いずれも平安時代末期の作。
-
こ 弘源寺
- [ 寺院 | 桜 | 紅葉 | 花 ]

-
京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町65
臨済宗・天龍寺塔頭の小寺。
永享元年(1429年)室町幕府の官領であった細川右京太夫持之が、天龍寺開山である夢窓国師の法孫にあたる玉岫
-
か 桂離宮
- [ 歴史的建造物 | 庭園 ]
-
京都市西京区桂御園
回遊式の庭園は日本庭園の傑作。
八条宮家の智仁親王が、「瓜畠のかろき茶屋」と呼ぶ簡素な建物を営んだのに始まる。広大な庭園には、古書院、中書
- [ 寺院 | 初詣スポット | 紅葉 ]
-
京都市右京区嵯峨大沢町4
[ 紅葉時期 11月中旬~12月上旬 ]
真言宗大覚寺派の本山。
嵯峨天皇による離宮嵯峨院建立が起源で、876年に恒寂入道親王を開山とし、代々天皇または皇統の人物が住持に就